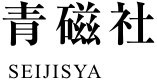青磁社通信第三十一号VOL.312020 年 10 月 発行
巻頭作品
秋燕
ウイズウイルスウイズ炎熱わが詩も
大盛カレーライスの如き日焼岩
くしやくしやのマスクの上の天の川
詩魂には自粛は無用天の川
子は詩の磁場なり桃は夜太る
三密は生まれつきなり八頭
我ら住むどこも彼方や秋燕
エッセイ
謦咳
この前、「レ・パピエ・シアン」という同人誌を読んでいたら、塩谷風月さんの次の歌に目がとまった。
寒椿の凛とした赤、岡井隆の後ろ姿はいつも厳しい 塩谷風月「レ・パピエ・シアン」九月号
岡井さんの後ろ姿の厳しさを歌った歌で、私は一読、心惹かれた。
ひとつの風景が蘇った。雨に濡れた椿の花と、岡井さんの後ろ姿と、石畳に落ちる雨の音。そんなものたちが、眼前にありありと立ち現れてきた。
あれはいつだったろう。そう思う。
そして、そうだ、あれは京都だった、と思う。
いろいろ調べてみた。分かった。あれは今から三十一年前の平成元年三月、京都の法然院に向かう参道でのことだ。東山の鹿ケ谷にあるその寺院で米田律子さんが企画した「古典をたのしむ会」があったのだ。椿が咲いていたのはその参道だった。
この時のことを岡井さんは次のように記している。
三月四日。「古典をたのしむ会」於京都。法然院まで、バスストップから雨中を歩いた。この道がよかった。法然院のひろい石段を登って行くと、赤い椿の花が散っていてそこで三脚を設置して写真をとっている男がいた。土地のアクセントで鋭く「椿を踏むな!」と注意するのにおどろく。もっとも注意されたのは寺門から下ってきた四五人の夫人達だったが。会は三十人ほどで内容の濃いいい会だった。会の休憩の時、法然院の椿の古木を見た。雨がとめどなく幹を流れ葉を洗い、わずかに咲きはじめた花を一きわ美しく見せた。(「未来」平成元年四月号・巻末後記)
私はこのとき「未来」に入って三年目、二十八歳だった。「古典をたのしむ会」のパネリストに選ばれて、緊張しつつも、張り切っていたのだろう。その私の前を当時六十一歳の岡井さんが歩いていたのだ。
当日は春の雨。法然院前でバスを降りると、私の前にカーキー色のジャケットを着てビニール傘をさした岡井さんがいた。十メートルほどの距離であるが、私は声をかけることもできずに、その後を歩いていった。
道の半ばまで来て彼は立ち止まった。足もとに赤い椿の花が落ちている。彼はまずそれを見下ろし、それから視線を上に移し、枝に咲く椿の花を見た。彼はほっと一息ついて、しばらくそれを見上げていた。
傘をすこし傾けた岡井さんの姿が、今でもはっきりと目に浮かぶ。この年、彼は豊橋の国立病院を退職し、医師を辞め、春から京都の精華大学に赴任することが決まっていた。岡井さんは、あのとき新しい職場になる京都の街を訪れていたのだ。新たな人生のとば口に立っていたのだった。
このときだけではない。岡井さんの後ろ姿はいつも孤独だった。私は、その後ろに立ちつくすことが多かった。
あのときもそうだ。
今から十五年ほど前、岡井さんを三重に招いて講演をしてもらったことがあった。講演の始まる前、彼は五階の窓に身を寄せて津の街を見下ろしていた。
駅の奥に森が広がっている。彼はその森を見て「向こうの方に美術館があるでしょう」と言う。「あります。県立美術館です」と私が答えると、彼は「昔、ひとりであの美術館に来たことがあってね」と言った。そして、
-ー苦しかったな、あの頃。
とつぶやいた。
それは、夢のなかの言葉のようだった。
岡井さんは多分、二十年前のことを思い出していたのだ。八〇年代前半の歌を集めた『αの星』に次の一首がある。
風上は朱のいろあはき美術館伊勢路をふかくくだり来にけり 岡井隆『αの星』
あっさりとした歌だけれど「ふかくくだり来にけり」あたりに、深い詠嘆と孤独が刻印されているように思う。このとき彼は五十五歳だった。歌集からははっきりと分からないが、崩壊しつつある豊橋の家庭を必死で支えようとしていた頃だったのだろう。「苦しかったな、あの頃」というため息の背後には苦い過去があったのだ。
謦咳に接す、という言葉がある。「謦」も「咳」も「せきばらい」という意味だ。私は岡井さんの私生活を直接に知ることはなかった。が、岡井さんの謦咳に接することによって、私は、人間の本質的な寂しさに触れることができた。それによって、私はすこしだけ大人になれたのだ。
知性のきらめきに触れる
佐藤弘子句集『磁場』

「寒雷」から「暖響」と楸邨の師系の結社で研鑽を積みつつ、二〇一三年から「小熊座」にも参加している著者の第一句集である。一九八三年から二〇一九年までの三十六年間の句から三百二十句を選んだとあとがきにある。ひとりの書き手が進化していく過程がスリリングな句集だ。
毛糸玉消え雑念の編み上がる
冒頭の句である。編み上がったものそのものを詠まず、「雑念」と片付けてしまうインパクトにビクッとする。初学の頃にこの切れ味、すごい。
赴任地は霧美しと夜の電話
一転、ロマンチックである。単身赴任中の夫からの電話だろうか。共に暮らさない生活にしばし酔いしれる気持ちが窺える。
はなびらの押し合ふ音の中にをり
こう書かれることによって私たちはそれまで聞こえなかった音を探し始め、あ、これかな、ああ、確かに「押し合ふ」だなあ、などと納得したりするだろう。桜時に思い出したい句だ。
ていねいに暮らせば沙羅のひらきけり
二〇〇五年から二〇一〇年の句をまとめた章に載っているので、「ていねいな暮らし」という言葉がネットスラング化する以前の句であろう。沙羅の清純な存在感が印象的だが、世代によって全く違う読みができそうな句だ。
吾亦紅くすぐつたいと柩の眉
「姉逝去二句」の中の一句。棺に納められた吾亦紅が死者の眉のあたりに触れている。吾亦紅の素朴な佇まいが幼い頃の記憶を呼び覚ましたのか、共に遊んだ頃のような笑顔で起き上がりそうな表情を眉だけを描くことで表現する。ストイックに表現された哀しみが心に刺さる。
厚みのある言葉を選び取る知性がきらめく一冊である。
樹に重ねる俳句人生
及川由美子句集『ぎんどろ』

「ぎんどろ」とはヤナギ科の植物の一種。葉の裏に毛が密生しており、銀白色に見える。宮沢賢治が愛したことで知られ、賢治が教師をしていた花巻農学校跡にある岩手県花巻市のぎんどろ公園には、多くのぎんどろの木が植えられているという。
『ぎんどろ』の著者はまさにその花巻市の出身。彼女にとってもぎんどろは親しみやすい木だったのだろう、句集を読むと折に触れてぎんどろの木を気にかけていることがわかる。ここ二年の句が収められた最終章の章題にもなっており、ぎんどろの姿に自らの歩みを重ねているのかもしれない。
ぎんどろの大樹を仰ぐ夏帽子
ぎんどろをとくとく上る春の水
ぎんどろは月の光を湛へたり
ぎんどろの幹のまはりの落葉踏む
自らの境遇を饒舌に語るタイプの書き手ではないようだが、時折登場する家族の句にハッとする。第三章「震災」の、それぞれ〈長女は石巻〉〈二女は南相馬〉という前書きのある見開きページには胸が詰まった。しかし私が一番印象深かったのは〈三女へ〉の前書きのある
春の月遠きひとりよつつがなく
であった。すぐ会いに行ける距離ではないのだろうか、温かい愛情と共に愛情だけではどうしようもない無力感が句の底にあり、だからこそ「つつがなく」と祈る。繊細な親心が春の月に託されている。
夢に来て夫は無口や花林檎
夫を亡くした後の句。夢に出てきたなら何か言いたいことがあるだろうに、というもどかしい思いと、林檎の花の初々しさがひたすらに切ない。
今読むべき歌人論
三井修エッセイ『雪降る国から砂降る国へ』

三井修のエッセイ集『雪降る国から砂降る国へ』は、近年になく内容豊かで刺激的な書である。「エッセイ集」と銘打たれているが、エッセイの域を超えた評論も多く収めていて読み応えがある。郷土の歌人に関わる評論や現代の歌人についての評論がある一方、アラブの国々に関わる貴重なエッセイもある。どの文章にも発見があり、読者を遺憾なく楽しませてくれる。中でも、私が強く惹かれたのが歌人論である。私自身、歌人論を長く書いてきたこともあるので、初めは三井の筆致がどの程度のものかを確かめようなどという大それた気持ちもあったが、読み進めていくとすぐにそんな気持ちは消え失せて、文章を読み耽ることになってしまった。とりわけ三井の郷土の歌人岡部文夫に関わる文章は、いずれも心に残る佳品であった。岡部文夫という歌人の魅力が存分に伝わってきた。しかも、岡部についての論考をある雑誌に連載しているとも書かれていて、それならそちらも早く読ませてほしいという願望が高まって仕方なかった。安直な歌や意味の取れない歌ばかりが詠まれている今の時代に、郷土にしっかり根を下ろして、言葉を疎かにしない岡部の歌は、もっと多くの人々に読まれるべきだと私は思う。あまりに歌が軽くなっている今、岡部の重い歌は、現代短歌への良き刺激となることは間違いない。
また、現代短歌の現状を厳しく指弾する「新しい歌の発見を」には、大いに共感を覚えた。ほとんど同感である。まず岡部文夫の歌を引用し、次のように述べている。
かねがね、私は今の歌壇の関心は一部の「有名歌人」に偏重し過ぎていると思ってきた。その人たちにスポットを当てることは理解できる。ただ、現代短歌は「有名歌人」だけが作ってきたのではないことも事実である。近現代の歌壇はごく少数の先鋭的で意識的な「有名歌人」をピラミッドの頂点として「先鋭的」ではなくとも、良質の作品を作り出す「中堅歌人」をその下に置き、さらに、新聞投稿や地域間短歌サークルに拠る無数の「無名歌人」を広大な底辺とする重層構造であったと思う。
このような現代短歌の把握に全く異論がない。新しいものにしか飛びつかない短歌ジャーナリズムの不毛に対する厳しい批判がなされていて、私はほとんど全ての論旨に賛成だ。
一つだけ非常に残念ことがある。ほとんどの文章に初出が示されていないのである。初出という具体性は、一冊にまとめられた本にとっては、実に大切なものだと私は考えている。つまり、発表された雑誌や時代が分かれば、読者には、次の探索の標となる可能性がある。例えば、岡部文夫について、更に読んでみたくなった読者は、初出があれば、きっと次の読書の計画を練ることだろう。その道が閉ざされているのは残念だ。
真面目ゆえのおかしみ
中保ふみえ歌集『越前和紙』

子育てが終わった頃から始めた短歌を結婚五十年の記念の年にまとめたという。平成五年から令和元年までの四百三十首が収められた第一歌集。
つたなくも歌詠むしあわせ感じおり遠住む母への思いの一首
ふるさとの越前和紙に清書する二尺×六尺わが歌のせて
巻頭の歌が「つたなくても」で始まるのは謙虚な人柄の所為だろう。還暦を迎えた記念に自詠歌のかな書き展を開いたという。
今も残るだるま印の薬箱ひらけば紙の風船ひとつ
十円玉ひとつ分だけ話したる赤い電話の消えしタバコ屋
渦巻きのニクロム線でパンを焼き掌をあたためし学生下宿
薬箱の中の紙の風船、赤電話のあるタバコ屋、読んでいて懐かしくて涙が出てくる。渦巻きのニクロム線は電熱で温める火鉢のことだ。筆者は餅やするめを焼いた記憶がある。昭和の時代から日常を丁寧に生きて、家事をこなしてこそ実感のある歌ができる。物を選ぶ目が良い。観察と修練の賜物である。
アイロンの余熱を今日も当てている吾のハンカチ犬のバンダナ
名を呼べば耳をぶるると震わせる犬とわたしは「ト」の字に眠る
犬の歌も味わい深い。ハンカチのついでとはいえ犬のバンダナにまでアイロンを当てるとは、その律儀さと犬への愛に驚かされる。寝るときの「ト」の字にも納得する。真面目ゆえのおかしみが表れている。堅実に子育てをし、主婦として嫁としての役割をしっかり果たす人だとわかる。
領収書はりて膨らむ家計簿に輪ゴム一本かける日の暮れ
そして集の最後はこの歌である。お疲れさま、ご苦労さまと声をかけたくなった。
中庸のよろしさ
田辺昭子歌集『最初が大事』

『翼のありて』に続く第二歌集。表紙には咲き初める白梅一輪が美しい。清潔な印象の一冊である。平成二十四年から令和元年までの三五九首を収めている。
精神の要でありしフランスの自然に還るを夫は望みき
機は熟しセーヌの川に散骨す 心を尽くし節度を保ち
フランスに余程深い思い入れがあったのだろう。ご夫君の遺骨を彼の地に散骨したという。思いの強さに驚かされた。
さりげなく野すみれが咲き梅が咲き亡夫の知らざる十年が過ぐ
明日はもうアメリカへ戻る娘らと行く伏見城内に茱萸の実拾う
最愛の夫を亡くしてから、師である中村秀子氏が逝き、娘さんが渡米するなど独りの時間を過ごさざるを得ないが、そこにはいつも花や樹があり歌にすることで心を宥める様子がみえる。
一粒のまだまだ幼き顔をして最初が大事と梅が咲くなり
存分に咲いたのだから今はただほろほろと散れさるすべりの花
花に託して詠まれた歌のどちらもが本心なのだろう。「最初が大事」と未来を見る目と「存分に咲いた」と満たされる心。たゆたいながらまだまだ人生と歌作は続く。道のりを愉しむ心が伝わり、読む人は温かな思いに包まれる。
母ゆずりの大中小の甕あるも今は中でよし青梅漬ける
秋草の十種がほどを束ねては墓参にゆけりこんな日もある
梅を漬けるにも中の甕を選び、墓参りに秋草を供える自然体の作者。中庸を選ぶ心に優しさを感じる。極端に走って破綻することのない懇ろな暮らしと歌がある。穏やかな生活の宜しさをしみじみと感じることのできる一冊である。
早咲きの桜が静かに散りにけり砧青磁の空の彼方に
裏切りとくぐもり
千種創一歌集『千夜曳獏』

中東在住の作者、四年半ぶりの第二歌集。若者言葉を積極的に取り入れ、韻律を柔軟にたわめて語るナイーブな文体は今も健在だが、本書では、そこに何かくぐもったものが追加されている。
あとがきにも「編年体ではない」と明記されているが、本書のⅡ章辺りからは、主に京都を舞台にした一連の恋物語として読めるよう構成されている。第一歌集『砂丘律』の推薦文の中で、私は「彼は描き出す。東京の片隅を。砂の降る国での日々を。そのどちらでもあり、どちらでもない時空間を」と書いたが、その延長線上として考えるならば、本書は、中東でも東京でもない場所ーー一種のアジールとして京都が選び取られていると解釈することができるだろう。
雨だから泊めてもらって長城のような座卓をはさんだ眠り
枯れるなら声は花かも 鴨川はいくつも声を浮かべ流れる
だめだとは私も思うと首肯いて、向こうへ、飛び石を、飛んでいく
どうやっても悔やむであろうこの夏をふたりで生きる、花を撮りつつ
友人関係から徐々に距離を狭めてゆき、恋人同士になる二人。その関係は甘く官能的だが、奇妙なほど刹那的で不安定だ。この恋に終わりがくることを、はじめから予期していたように。
美術館の外には薄い池がありお互いの裏切りを話した
きんぎょとは火の魚だと説くときに焦げだす良心のかけらは
この雨は同じ。透けるユダの手の銀貨を濡らした春の小雨と
裏切りや良心、罪、罰といった言葉が時々顔を出す。まるで、生きて恋をすること自体が何らかの禁忌に触れているかのような、危うい感覚。途中、小早川秀秋やユダをテーマにした一連が出てきて面食らったが、裏切りについて考えるうち小早川やユダに心を寄せていったと考えると、一応は納得がいく。ただ、なぜそこまで思い詰めているのかは、茫漠としていてよく見えてこない。「ぼく」と「あなた」の顔もほとんど描かれない(「あなた」は手と髪、後ろ姿、そして声だけで存在する人のようだ)。
風邪ならば梨を剥いて差し上げたい 梨崩し、ってそういう遊びっぽい
こうした言葉遊びさえ、言葉によって自由に羽ばたくというより、むしろ心の重さを紛らわすための苦しい営みのように見える。
繰り返し読むうち、私はこの物語の語り手「ぼく」に対してもどかしさが募ってきた。罪の意識を抱えつつも、その本質に迫ることを避け、失った恋を感傷的に噛みしめ続ける「ぼく」。全く共感できない。いや、共感はできなくても構わないのだが、「ぼく」の哀しみはそれとして、短歌の文体にまでくぐもりが生じ、一冊全体に霧が立ち込めていることには疑問を感じる。この霧は晴れるのか、今後さらに深まるのか。第三歌集、いつまででも待っています。最後に、やはり感傷的ではあるが、良い歌だと思った一首を引いておく。
どの蝉も帰るべき巣のないことが流砂のように心を走る
熟練の技の味わい
石川満起乃歌集『藍の紬』

第三歌集。白地に和服の柄を思わせる表紙の装丁が上品だ。和裁を生業とする丁寧な暮らしの中で、短歌の技を磨いてきた結実の歌集だ。一首一首に工夫があり読みごたえがある。
蝉の羽のようなコートを縫う指を五月の風が時にくるわす
生き物のにおいじわりと放つなり藍染深き紬を裁てば
指貫をはずせばふっと緩みたるからだの芯へ空気を入れる
薄物のコートを注文するのは着物の通だろう。その期待に応えるための緊張が伝わる。五月の爽やかな風を受けながら、気を緩めてはならないと強く意識しているのがわかる。意識すればこそ「くるわす」と敢えて言ってみせるところに技を感じた。次の歌には集題となった言葉がある。藍染の独特のにおいは実際に生地を裁つ経験をしないとわからないだろう。布地の命との対峙を思わせる。そのためだろうか、指貫をはずしたときのほっとした気持ちを詠んだ歌も魅力的だ。指貫という小さな道具が、縫うときの緊張と一息をつく解放との通路に見えてくる。
斉藤斎藤さんのさいの字が同じでないこと昨日気付いた
草萌えの表紙一冊書架にぬき岡部伊都子に出会う午後なり
結社「水甕」で藤川弘子氏らと共に研鑽を積んできた作者が、短歌をはじめとする本に広く親しんできた様子がわかる。
甘露煮のひらたき鮎に茶に染まる卵詰まれり秋の灯の下
鮎の甘露煮がまさに追って目に浮かぶように描写されている。「ひらたき」が適切でうまい。季節感もあり秀逸な歌と思う。
六ヵ月の余命と若き医師の声まっすぐ我の肺をつらぬく
歌集は五首一組の連作が続く構成になっていてこの歌が最後。あとがきも著者略歴もない。闘病されているのだろうか。熟練の歌の味わいをもっともっと知りたくなった。
くいくいとホームを歩く二羽三羽鳩の羽色左右対称
圧倒的な「従軍時の短歌」
米田登歌集『米田登作品集』

全歌集や作品集というものは、既刊歌集が中心で、第一歌集以前の若書きや最終歌集以後の作品、若干の拾遺が加わる程度であることが普通だが、驚くことに本書はなんと六割以上が歌集未収録の作品である。なかでも「従軍時の短歌」(二八七五首)だけで既刊歌集四冊の総歌数に並ぶ。
戦ひの不利なるを知らぬ家族らの今よりゆきて儲けむとするか
女らを連れて渡りゆく軍の業者が昼より酒をのみて慣れ慣れし
国内での教育訓練を経て大陸に渡ろうとする場面。満州へ行けば商売になるだろうという人たちと出会う。いわゆる「慰安所」関係者は「軍の(、、)業者」と認識されている。
若くして不潔になりゆく友のこと肯ふごとく語りてねむる
妻子らと三年さかりてある兵の妻恋ふる言葉に吾は報いむ
その「慰安所」へ通う友と、距離をとる兵。「肯ふごとく」というあたりの苦み、立場のある「報いむ」に注意して読む。ヒューマニズムを心の底に持ちつつ現実的であるというのは、戦後の米田登作品にも通じるものだろう。
軍の中では輜重=輸送部隊であり、当時としては馬が主な輸送手段であった。
日本馬の日本馬であることゆゑに総て将校乗馬となりをり
額髪なでてわがゐつ顔よせて甘ゆる満馬はかはゆきものを
現地調達した馬は低く見られていたのか。
倒るる馬は駄載もろとも棄ててゆく過重積載をにくみつつゆく
過重積載を言へどわからぬ副官のまへ怒りこらへて叱られてをり
われらただ馬休ませてをりし二日師団は敵を討ちて迫りき
泥の中を這うような無理な輸送は馬も荷も捨ててゆかなければならない。捨てれば叱られる。攻撃はされるが、直接の戦闘ではない。「休ませて」は、疲労の極であるし、次の輸送に備えなければならないということでもあるだろう。
従軍もさまざまだが、よく知られた宮柊二や近藤芳美、また米田との近さで言えば香川進ともずいぶん違った情景がここには展開されている。
遺品を整理していて出てきた原稿であるという。「呼び出され叱られゐしが吾が書きし日々の記録は偽りならず」という作品もあるが、没収・破棄されることなく残ったのは幸運だった。年譜によれば「昭和十七年から十九年の間約三千首の短歌を詠む。一部を『詩歌』に出詠する。」とある。それが原型であり、「詩歌」掲載分も、本書のなかで比較することができる。精読することでさらに見えてくることがあるだろう。
数とサイズ
森絹枝歌集『よもぎ野』

『よもぎ野』は第一歌集。「あとがき」に「ながい年月、わたくしの心を占めてきた短歌がしてくれた役割を少しでも多くの人に、この歌集をとおして感じ取っていただければ嬉しい」とあるが、十分に感じ取ることができた。
一頭と数えるのよと教えられ紋白蝶は巨大になりぬ
目に見えぬものをついばみ雀の子日暮れにかすか大きくなりぬ
山塊の天辺に立ち蟻のやうに小さきわれは水を欲する
よどみなくとんぼの群は流れゆく大雪山に腰掛けをれば
ちょっとした心理が加味されることによって、紋白蝶は巨大になり、雀の子はかすかに大きくなる。勿論、現実にはそういうことはあり得ないのであるが、断言することでサイズの変化が妙な説得力をもつ。そこが面白い。主体自身も蟻のように小さくなったり、ガリバーのように大きくなったりしている。サイズの変化をもたらすことで、場面がいきいきと動きだす。
ゴシック体15ポイントなら見えると言ふ讃美歌入力し一九二曲目
目の位置の十センチほど高ければわれのみが見しナキウサギのかほ
ニンニクは十月二十日に土深く植ゑるがよしとニンニク届く
倍率を96%に設定し篆刻教室の手本をコピーす
数を詠み込んだ歌はどれも面白い。15ポイントなら見える。それ以下では見えない。たしかに世界は数字で刻まれており、境界が区切られている。どうしてもその数字でなければ、うまくいかないのだ。ニンニクを植えるのに最適の日があったとは。「科学的根拠は?」と問うのは野暮というものだろう。断言の小気味よさ。かけがえのない数字はかけがえのない暮らしを支えている。そのことに気づかせてくれる歌である。
現場で何が起こったか
澁谷義人歌集『アジア放浪』
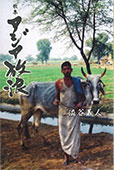
『アジア放浪』は第一歌集。作者は一九八八年から海外サイクリングに二十回挑戦し、単独でアジア各国を巡ってきた。「自転車のゆっくりとしたスピードで、現地の人と会話し交流を深めた旅」(あとがき)の記録である。
タクラマカン沙漠に浮いた塩分を集め担ぎぬウイグルの子ら
ニワトリのハラワタ引き出す右手にてほつれ毛直し少女微笑む
物乞いの小さな少女力込めわが手わが脚自転車つかむ
子どもたちの姿を活写して生彩がある。沙漠に塩が浮き、それを集める。ニワトリのハラワタを引き出す。生活即労働である。作者は見聞をありのままに提示し、感傷や感想を交えることがない。ベトナムで出会った物乞いの少女もいきいきと描かれている。現場のもつ臨場感が映像と共に迫ってくる。
古本の満州地図に書き込まれし「大連高女」のインクがにじむ
雄たけびをあげつつ駅に迫り来る列車に残る「満鉄」の文字
日本の兵士が刀を振り下ろす絵から少女は目を離さない
「大連高女」「満鉄」といった歴史性を帯びた固有名詞が、生々しく立ち上がってくる。「満鉄」の文字を残した列車が、今もなお走っているとは驚きだ。侵略の歴史がぬっと顔を出したような不気味さがある。三首目は中国・江南にて。加害者は戦争を忘れたがるが、被害者は忘れることがない。戦争はまだ終わっていない。
十年前の前田明のプロレスが放映される最南の宿
ドラえもんナウシカポケモンタマゴッチ「日本」が占めるチェンマイの街
異国の地での「日本」との出会い。現地の人々との交流は「日本」を見つめ直すきっかけになったにちがいない。
認識を発見する
熊村良雄歌集『うたふ鰭』

『うたふ鰭』は第二歌集。
氷塊に眠れるものを目覚ましむ温暖化とは世にいひ広げ
除夜の鐘に騒音の苦情ありとよ大いなる風の吹き渡るべし
七割はみづといふ汝(なれ)を抱けば決壊のごとき思ひかある
地球温暖化、騒音、決壊という現代的な言葉を用いている。「氷塊に眠れるもの」の実体は明らかにされないだけに、不気味さは倍加する。除夜の鐘までもが騒音として糾弾される。クレーム社会の底なし感をやんわりと受けとめ、シニカルに批評する。「抱く」という親愛的な場面において、「決壊のごとき思ひ」を歌う。ボルテージがどんどん上がる。危険水位まであと少しだ。破壊的なエネルギーの美しさと危うさ。
翳のさすあたりに泛む一対の白足袋のやうに見えてゐるもの
たひらかに扇をかざし歩み出でぬはじまりの如く竟りのごとく
「白足袋のやうに見えてゐるもの」は「白足袋」と「白足袋でないもの」との間に、「はじまりの如く竟りのごとく」存在する。「ある」ものと「ない」ものとの間を言葉で捉えようとすれば、こういう表現になるのではないだろうか。哲学めいた深遠な世界を言葉で切り拓いている。熊村良雄さんは七月におなくなりになられた。心より御冥福をお祈りいたします。
妻への恋文
上野直歌文集『螢烏賊』
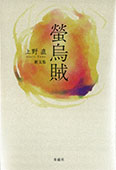
これまで「前頭葉側頭葉変性症」という難病指定の認知症の妻を介護されて来た歌集を三年ごとに三冊出されている作者。
この三冊で終りにする予定だった作者が歌文集を出すきっかけとなったのは、数年前に、ご自身まで「全身性アミロイドーシス」という難病が発症したことであった。モニター越しに見る心臓に映し出されたものが、光を放つ螢烏賊のように見えた事から歌集の題名とされている。見開きに作品一首とエッセイを記される一冊は、命を失っていてもおかしくなかった経験を記され、ペースメーカーを入れる生活になられても妻を見守り続け、どこまでも前向きで、生きる希望に溢れている。
きみや先われや先かと案ずるにきみを遺して先には逝けぬ
これしきのことで負けてはいられない妻看ることはわれの天命
けさのこの篩にかけた笑顔だけ疾く持ちゆかん色褪せぬうち
妻は目で身振り手振りに口と目で会話している介護のわれは
宮崎在住の作者は、お元気なころは一通りの家事を済ませ、途中の自然林の移ろいを楽しみながら、愛車で妻の入院先へ向かい、胃ろうとなった妻に夕方まで付き添う毎日だった。発病後は体力気力とも失せて、挫けそうな思いを抱えながらも、介護を天命と詠む。毎朝一番に鏡に向かって最高の笑顔を選び妻のもとに駆けつける。そしておどけるような身振り手振りの会話で妻の笑顔を引き出せた時が最高に幸せだと書かれる。
なぜ作者はそこまで出来るのかは、元気だったころの妻がどんなに出来た、素敵な方だったのか、また脇で支えてくれる二人の娘の存在なども詳細に記されて、心温まる一冊である。
前頭葉側頭葉がいま一度甦らずともどこまでも恋
青春性と予感
朝日泥湖句集『エンドロール』

先日「散在」した俳句集団「船団の会」に所属した著者による第二句集。横書きの文字組の帯が映画のエンドロールのようで、タイトルとのリンクを思わせる。
うどん茹で過ぎやん亀鳴いとるやん
ゆるゆるとした噛みごたえのうどんのようなしなやかさで関西弁を巧みに聞かせる。虚の季語だからこそ魅力が増しているようにも感じる。
夜行バス降りれば釧路啄木忌
啄木が一時期働いた釧路に降り立つ感慨を、夜行バスという比較的安価な旅の手段と共に提示した句。青春のネガティブな心模様を詠んだ啄木の忌日に寒さが和らいだ北海道に降り立つという、みずみずしい旅情とかすかな厭世の気分が溢れる舞台設定も心憎い。
カツカレー泳げないけど海が好き
海の家でカレーを食べながら海を眺めているのだろうか。海と食べ物との取り合わせは食べ物が妙に不味そうに見える時があって面白いのだが、この句のカツカレーは中七下五の無邪気さに引きずられるからだろうか、とても美味しそうである。
行く春を惜しむ近江のオムライス
ひたひたと闇迫る湖裕子の忌
時雨忌や義仲寺の角らーめん店
湖光り比良はしぐれて湖西線
近江を詠んだ句の多彩さにも着目したい。一句目を音読してみると「惜しむ」「近江」「オムライス」とO音とマ行の組み合わせが句の中に繰り返し登場する気持ちよさに魅了される。二句目はこの句集が青磁社から出された縁を感じる。三句目や四句目での生活感溢れる詠みぶりも魅力的だ。タイトルとは裏腹に、句業の深まりの予感をたっぷり秘めた句集である。
福音書を胸に
安藤純代歌集『ナルドの香油』

敬虔なクリスチャンであり、障害を持つ息子の母でもある作者。万事控え目な詠みながらも、深い信仰心と思索に裏打ちされた作品は一首一首が心の奥底に響く。宗教と息子を両輪に詠みながらも折々に詠まれる反戦の思いに圧倒されるが、それは平和を希求する思いの強さでもあるのだろう。
ああまるで大きな木蔭にゐるやうだ高機能自閉症(アスペルガー)の君に添ふとき
すんすんと伸びる麦の穂むぎの風 健常児の子育てわれは知らざる
すすき原、銀の茅原子と分けゆく空の巣症候群(エンプティー・ネスト)われには遠く
うまくても下手でも必ずほめくるる子はわが歌を風のごと聴き
二、三首目のような屈託や不安も詠まれるが「銀の茅原」の先には救いがあるように美しく、穏やかで優しい息子さんの作品も多く、大いに救われていることが伝わる。
学名はベロニカ・ペルシカかの日かの汗をぬぐひし瑠璃にてあるや オホイヌノフグリ
熱線も瓦礫もいまだこの背に受けしことなく母と呼ばるる
一日を苑のおもてに在りたるや葡萄園に職を求める人ら
花の名から処刑場へ向かうキリストの汗をぬぐった布を思い、長崎では被災した信徒を思い自己を省みる。低賃金で働く吾が子からマタイ20章を思う。冒頭近く子の合同就労説明会が詠まれ、九年後の巻末でも九度目の合同面接が詠まれ、社会の受け皿の在り方という問題も内包する一首である。日常でも旅先でも多くが福音書を胸に、戦争を、自己を振り返り奥深い。
わが罪は歌にならざる重さもてわれに迫れり十字架のもと
また、父の突然の死を受け入れてゆく様子や、残された年老いた母との暮らしなども丁寧に詠まれ印象的であった。
短歌を杖に
みずのまさこ歌集『虹の片脚』

平成十一年から十歳の長男が二十八歳で結婚されるまでを、その時々の出来事と二人子の年齢を各小題に添えられ、冷静に作品化される。二人子の成長の記録でもあるのだが、平成という時代は激動の時代であったことに改めて気付かされる一冊。
みづみづと潤んだやうな目の少年世界が歪むさまをみてをり
銃を持つ若き兵にも母がゐて眠れぬ夜の月を見上ぐる
われの子が引き金をひく 夕焼けの空はそんな明日へもつづく
米国同時多発テロからの社会情勢を詠み、どの作品も我が子というフィルターを通し世界を見詰め危惧している。
もう誰も聴いてはくれぬ子守唄口の端にのす今宵はひとり
子に執し子離れもせず子を喰らふ魔性はきつと母性なるらむ
折々に詠まれる子離れの寂しさに深い母性と葛藤が伝わるが、ただ寂しがるだけではなく、子のために行動に移し、積極的に過ごしながらも丁寧に日常を掬い取る。
そんな作者を襲うのは社会不安だけではない。二千年問題での激務中に倒れる夫、何人かの同年代の友人知人の死。それは誰にも他人事ではない現実を突き付けて来る。また、子ども達の反抗期や重くのしかかる高齢の両親の介護。誰もが通る道といえども、しっかりと「人生」を詠む。作者がこの第二歌集を編むきっかけとなったのはご自身がクモ膜下出血出で生死を漂ったからである。奇跡的に命を繋いでもらった作者は「短歌を杖に思考を取り戻していった」と書かれる。そして人生で一番若い今、息子たちへの思いを纏めたかったことを記される。
思春期の訳のわからぬ反抗をAIもする…かもしれぬ闇
増々混沌とする世界、今後も冷静な視線で詠んで頂きたい。
世界への愛の体温
大島雄作句集『一滴』

「青垣」代表の大島雄作の第五句集『一滴』は、にぎやかで動的だ。体温、肉声、命のエネルギーに満ちている。そのゆえん、一つは詠む対象。作者自身も「生き物、特に動物の句をよく作ってきた」(あとがき)と述べるように、句集のそこここで、この世界に生きる者たちがのびのびと呼吸している。
雪しろや掌を押し返す牛の息
みつみつとアロエの肉や夏旺ん
土旨しうましと蚯蚓くねりたる
子を産んで猫に杏のにほひあり
よりきてはさつと子雀ちりぬるを
雪の冷気の中、掌を濡らす牛の息のぬくもり。みな息たえだえの真夏の日差しに、肉を太らせるアロエの強さ。全身で土を喜ぶ蚯蚓の恍惚。子を産んだ母猫の、杏のような甘い匂い。子雀たちの幼い動きを、いろはの言葉で示した遊び心も楽しい。生き物たちを風景として静的に写生するのではなく、動きや感触を描き込み、いきいきと動的に詠むのが大島流だ。
枝豆を飛ばしてビートルズ世代
角も丸もこころのかたちおでん鍋
褒美なけれど蓮の実の飛びにけり
麻服の皺ほど仕事してをらず
人間もまた動物の一つ。一句目、居酒屋で枝豆をつまみ、同世代と往年の名曲を語り合う、気のおけない時間。「飛ばして」の勢いに、場の臨場感が宿る。二句目、おでんの具の四角も丸も「こころのかたち」と定義した。ときに尖り、丸くなり、おでん鍋は本音の心を引き出す。三句目、我が褒美は蓮の実か。社会からはみ出た俳人としては、飄々としてそれもまたよし。四句目、麻服の皺のつきやすさに諧謔を滲ませた。どの句にも、喜怒哀楽を抱き込んだ人間が、今を生きている。
体温を感じさせるもう一つのゆえんは、その詠み方だ。
手鞠つく地球しつかりしてくれよ
かかとから歩かう冬野はじまるよ
湯豆腐に利尻昆布を敷いてやろ
てきたうや五人囃子の並び順
こう呼びかけると、地球も旧知の友人のようだし、一緒に冬野の危うさを歩きたくなるし、湯豆腐も赤子のようでかわゆいし、そっか五人囃子も適当に並べていいんだ、と肩の力が抜ける。言葉で示される強い連帯は、世界への愛そのものだ。
蜩の木の鉛筆があらばほし
『一滴』の中で一番好きな句を引いた。蜩の鳴く木を削って作った鉛筆からは、きっと、切なく身に迫る言葉が生まれるだろう。鳴き終わる蜩を引き継ぐように、命を繋いで書く。世界への愛の体温に触れた読後、私の心も自然とぬくもっている。
ふるさと恋
小谷稔歌集『大和くにはら』

歌集『大和くにはら』は小谷稔先生の歌集『黙坐』(平成二十八年刊)以後の作品四六七首がおさめられている。先生は平成三十年十月に九十歳で亡くなられた。平易な言葉による生活と思いの写実表現を大切にされた先生の最晩年の日常詠である。
この耳も足もいつまで達者なるか月に出る会十指に近し
八十代の先生が、近畿一円の「新アララギ」の歌会に出向いて後進の指導に尽力された。
動脈瘤も腎の石も暴れることなかれ八十八の吾の道づれ
歌の会の帰りの道に癌のことも告げて医の友あるは安けし
夜明けまへの涼しき時に机にてもの書く知恵も老いて知りたり
戻り来し夜の涼しさに子規論の新書版一冊読みおほせたり
われのみの役なれば妻の背に赤きヘルペスに夜々薬を塗りぬ
さつま藷のひげ根とりつつ畝に座り汗ばむことなきよき日和なり
宿痾に新たな病も加わる。さかんに原稿を書き、読書された。老年の日々を分かつ奥様へのいたわりも懇ろである。秋の日差しのさわやかな菜園の畝に安らぐのは帰農の翁の姿である。
淡々とうたわれる老年の日常詠にあふれふるさとへの思いがこの歌集を特徴づける。直近の記憶が消えて、幼少年期が鮮明に甦るのが老年期と言われる。
月冴ゆる冬のある夜思ひ立ち電車に乗りて明日香を訪ひき
大和の歴史的文化的遺産、古代に変わらない景色をこよなく愛して歌に詠んでこられた。奥明日香は過疎化で消滅したふるさとを重ねての逍遥であった。
庭の宴終へて見上ぐる北空の竜座は跳ねる形ゆたけし
植物園の稲穂に触るるさへ辛しわがふるさとはなべて放棄田
金繰りに苦しみし父わがためのクレヨンも半紙も上質なりき
学寮より帰るわがため母は誰にも採らしめざりき桃もトマトも
一首目ははらから六人が故郷に集った盆の夜の星空。岡山県北部の新見市より山坂を登った限界集落である。生計に苦しみながらも子供の教育に熱心な両親に養育され、多感な少年期を過ごしたふるさとは先生の終生のテーマであった。フラッシュバックのように蘇る父母の記憶。すでに消滅したふるさとへの思いは痛みをともなう。
次は、命の根源を潤す水を求める掉尾の一首である。
薬剤の副作用にて喉渇きふるさとの天然水ひたすら恋し
亡き人とひとつとなりて
雁部貞夫歌集『わがヒマラヤ』

あへぎつつ登ればハーブの香り満つ氷河迫りし山の斜面に 『崑崙行』
ピッケルを幾度もはね返す蒼き氷足場を刻む掌のむくみたり 『辺境の星』
天に近きこの草原に早駆け(ギャロップ)す吾が身も馬もひとつとなりて 『琅玕』
三十キロの荷を負ひ進むこの氷河蝸牛の如き歩みなれども 『ゼウスの左足』
摩竭の大魚いかなる魚か一目見む烏萇国(ウジャーナ)の谷けふ溯る 『山雨海風』
一九六六年から二〇〇三年にかけて合計十五回に及ぶパキスタン北部チトラール(西域の歌も含む)に於ける踏査行で得た約千首を既刊の五歌集から自選した重厚な一冊である。各歌集から一首ずつ挙げたが、どの歌からも雁部の肉声が聞こえて来て、レトリックなど何するものぞ、歌い方は単純にして簡明、力強い響きを持っている。『わがヒマラヤ』には歌だけでなく、原著に併載のヒマラヤ関係の充実した臨場感あふれる紀行文や各歌集の解説文も収められている。チトラール地域を記述した文章は少ないようなので、その意味でも貴重である。
…山を愛し旅を愛し家族を愛し友を愛す。雁部は人生を愛する歌人である。…
本書のために本多稜氏が総解説として書いている「『わがヒマラヤ』が拓く作品世界」から引いた。山、旅、家族、友、そして人生を心から、いや、肉体から雁部は愛しているのである。
時おきてザイルは強く我が掌引く君の呼吸を伝ふるがごと
妻捨てしそしりに耐へつつ魂(たま)こめてヒマラヤ書きし一生(ひとよ)尊し 『崑崙行』
落合先生たまひし古き印度図に法顕踏みしルート確かむ 『辺境の星』
雁部の歌には亡き人への鎮魂と敬愛の念が深く滲む。コヨ・ゾム登攀中に逝いた友である「君」の呼吸と共に雁部自身の息づかいも伝わってくる一首目。悲痛だが、実に温かい。二首目、妻を捨てた譏りに耐えながら「魂」を込めてヒマラヤについて書いた深田久彌の一生を敬する心。三首目、師の落合京太郎が呉れた古いインドの地図を手にしながら、中国東晋時代の僧が踏んだルートを確かめる。雁部の歌には死者の魂と肉体が張りついている。死者の魂、肉体とひとつになって、一緒に呼吸をしながら、自然を歌い続けてきた雁部。歌と共に生きる真摯な姿に私たちは勇気をもらう。最後に集中からコロナ禍にある混迷の時代にどう生きたらよいかを指し示す一首を挙げよう。
水たぎる谷底見るな前を見よこの掛け橋の真中を進め 『ゼウスの左足』
同時代を生きる
林充美歌集『樹雨のパラソル』
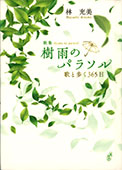
短文と歌で平成三十年の一年間を綴った第二歌集。ふらんす堂の『短歌日記』に興味を覚えたとあとがきにある。
天空にクレーン操る大男のくちもと約しもの食べるとき
お店屋さんごつこしたよね木の下で葉つぱのお札をポッケに詰めて
一首目、「天空にクレーン操る大男」という大胆なカットと対をなすかのように視線の収束する「くちもと約し」が印象的だ。歌の前の〈1/16(火) テレビ番組の「サラメシ」を見ると、ホモサピエンスとしての連帯感が生まれるようでホッとする。〉という短文に、映像を見ての作とわかるが、臨場感があり、同時代を生きる人々へ共感する作者の思いの丈が伝わる。二首目の前には〈1/25(木) 仮想通貨流出事件が波紋を広げているが、そもそも仮想通貨って何?〉とある。幼年期の無邪気な思い出の歌ではなく、「葉つぱのお札」に「仮想通貨」への疑念が重ねられているのだ。詞書と合わせて読むことで、背景にある社会への問題意識が浮き上がる。
光回線めぐる地球の秋の日に君へ手書きの文書きてをり
夜の河となつて煌めく街の灯のそのひと粒にむかひて帰る
一首目、「光回線めぐる地球」に、インターネットの地球規模の普及を表す。そんな中、君へ「手書きの文」を書く作者。二首目、大河のごとく集まり煌めく無数の街の灯の、「そのひと粒」である我が家の灯に向かって帰る。いずれも、時流に流されず迷いなく進む作者の姿が垣間見える作品と思う。
いくたびもモデルチェンジし進化する車のやうなウイルスあるべし
〈12/8(土)、インフルエンザの予防接種を受けた〉際の歌。技術革新の進む世の中にしてウイルスの進化に追いつけないという、令和二年の現在にも切実な内容を含む一首である。
旅と接続する日常
倉成悦子歌集『ターコイズブルー』

作者の第一歌集。日常詠と旅行詠を中心に構成されている。
古物屋に等身大の駱駝あり目の抜けし穴に風吹き通る
ウイグルの遺体を包む布買いて藍に染め首に巻く夏の来ぬ
クルドの人多く住む町の市場にて求めし刷毛のいよよ朽ちたり
一首目、「等身大の駱駝」とは店頭のオブジェだろうか。目の穴を吹く風に、砂漠を吹く一陣の風が想起される。二首目、ウイグル族の葬儀では遺体を清めて白い布に包むという。その布を利用し首に巻くストールとして使うとは少し驚くが、旅の記念の品を日常に活かす、作者なりの流儀かもしれない。三首目、「日本人を初めて見たという人らに囲まれ刷毛を一つ買いたり」とうたった一九九八年のトルコ東部への旅行で求めた刷毛だろう。「いよよ」に使い続けた年月が偲ばれる。海外の旅から遠ざかっても、その記憶は常に親しく傍らにある。
コンビニでばあちゃん(・・・・・)と呼ばれベトナムの青年に代わり送付票書く
平穏な七十年はたまたまのことにはあらず九条あるゆえ
一首目、日本語が書けず困っていたのか、「ばあちゃん」と親しみをこめて呼びかけるベトナムの青年に、迷わず手を差し伸べる作者。二首目、戦後の平穏は「たまたまのことにはあらず」と、憲法第九条の存在意義を強調する。これらも、旅を重ねた経験に培われた行動と思想であろう。
マルクスだレーニンだなどと気負いいし男もただの老人になる
爪をなめ尻をなめたるその舌で私の顔をなめにくる猫
夫と飼い猫に対するまなざしは寛容で、微笑ましい。彼らもまた、人生という旅の、傍らに居てくれるかけがえのない存在であると再認識させられる。
戦後史の一面
西村尚歌集『言の葉』
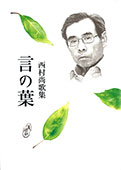
西村尚さんとの拝眉に浴したのは一度だけである。
姫路文学館で開催された「'60年 ある青春の軌跡歌人岸上大作」展のときであった。舞鶴から竹輪を土産に駆けつけて下さった。「お心入れによって盛会だったことを謝す」旨のハガキを「飛聲」一六〇号の高瀬隆和追悼歌掲載のページに今も栞っている。その初対面のとき禍々しいシーンを思い出した。
岸上大作と高校時代から交友があり岸上の人と作品の顕彰に残生を捧げることとなる高瀬隆和さんが、昭和三十五年(一九六〇)十二月五日、神戸での就職試験を終えて上京、久我山の下宿に帰ったところ大家さんに岸上の死を知らされた。
岸上の下宿に駆けつけると当時、国学院の大学院生であった西村尚の采配で、四畳半の狭い部屋いっぱいに布団がのべられ、岸上が寝かされていた。白い布で覆われた岸上の首にロープの跡が生々しく残り、彼の人生の終焉を見た。 高瀬隆和著『岸上大作の歌』(雁書館)より
この五十年後の西村さんの作品
岸上大作の死んで今年は五十年即ち我の生きてる時間
岸上の没後五十年展、百年展は知らぬよ姫路 われ老路(おいぢ)にて
追悼歌でも単に憐れむだけでない兄貴気質の滲んだ歌である。
平成二十年(二〇〇八)、高瀬隆和さんは肝臓癌のため六十九歳で逝去した。兄弟のような仲だった西村さんの落胆は深かった。「飛聲」一六〇号に「『卯月大変』…高瀬隆和死す」と題する追悼歌二十首を発表しこの歌集に全作収めている。その代表作
柩なる高瀬に会はず物言はぬお前に言葉溢れむゆゑに
晩年を早めし高瀬、晩年を生きとほしたるあはれ七十年
沢口芙美さんは平成二十六年(二〇一四)十一月、西村さんが他界したとき悲しみが伝播されたように愛惜の念を詠んだ。
冬の夜を遺書を前にしうなだれゐき高瀬隆和、西村尚と
岸上の死の悲しみを知る人ゆゑこの世にはまだ居てほしかつた
前後するが沢口さんは岸上の「血と雨にワイシャツ濡れている無援ひとりへの愛うつくしくする」の「ひとり」である。
前記の「…ある軌跡展」では『評伝・岸上大作 血と雨の墓標』の著者小川太郎と沢口芙美さんの対談があった。沢口さんが書けなかったこと、詠めなかったことを聞き出すイベントであった。終った翌日、高瀬、沢口、竹廣裕子(姫路文学館学芸員)と著者とで神崎郡福崎町西田原に建立された岸上の真新しい墓に詣でた。
誰も寡黙であった。
拙稿に登場した方々全ての身心に昭和史の暗い恥部が宿っている思いを深くした。
孤独とはなにか
桑原正紀歌集『秋夜吟』

本集は著者の第九歌集、長く勤めた教職を辞し、七十歳になるころまでの四年間の作品を収める。
ひさびさの朝のラッシュの車中にて孤独するどし退職者われ
撒水をしてノックせしグランドの夏の光を眩しみて立つ
ラッシュの車内に揉まれ勤務先に向う人々の中に誰にも知られぬ「退職者われ」の意識が孤独感を際立たせる。ふと懐かしくなって訪ねた高校の野球部は遠征中、顧問として選手にノックをしたグランドの夏光の中に立ち尽くす姿がうかぶ。
缶コーヒー買ひに自販機まで歩む未明の路地を影三つ走る
キッチンを磨き了へたる午前二時こころにしんと顕(た)つ姿あり
昧爽(まいさう)のしづけき天と地の間の木ぬれに鳥のいのち身じろぐ
未明に缶コーヒーが飲みたくなって自販機まで歩み、町猫たちに遭遇する。無心にキッチンを磨き了えたとき心に顕つのは、長き不在の妻の笑顔だろう。退職により、真夜中も未明も自由に使える時間になった。昧爽をしんと覚めている作者の孤独ないのちは、身じろぐ鳥のいのちの拍動にかさなる。
病室で花ばさみ捜しゐるわれに「タンスの中を見て」と妻言ふ
晴天をあふげばいつも車椅子日和とおもふわが習ひ性
ポケットに蜜柑三つを入れてゆく施設の妻へ年玉として
妻が脳動脈瘤破裂で倒れてから十四年、日課のように病院に、今は施設に通いつづけている。夫が傍らにいれば、病室はタンスに細々したものをしまう妻の部屋になる。青空の日は妻の笑顔が広がる「車椅子日和」、二人で越えて来た時間が尊い。
あをぞらに飛白(ひはく)の雲の浮くけふを原子炉がまたひとつ目覚めつ
何かヘンだ憎悪が徐々に剥き出しになりてゆあ〜んと世界はゆがむ
孤独な時間を世界とつながり目を見開いている。東日本大震災から数年がたち、ひとつまたひとつと稼働を開始する原子炉。
二首目は中原中也の詩の「ゆあ~ん」で軽い詠い口にみえるがこわい歌だ。歌集刊行後に遭遇するコロナの時代の分断と孤独にゆがむ世界を予感しているようだ。歌集巻末に次の一首をおく。
孤独とは負(ふ)ならずまして恥ならずしづかに己かへりみるとき
一人一人が深い孤独に向き合うコロナ禍の時代、孤独とはな
にか、静かに靭く問いかける歌だ。それは大切な人との繋がり
を手離さないための問いかけでもあるだろう。
ユーモラスな言語感覚
櫻井八重子歌集『もう振り向くな』

退職の願ひを出しての帰り道軽やかにして もう振り向くな
親となる若き等前に講演す一助産師の置きみやげとして
退職願いを出したその日の帰り道の心境は、職の現場から引く一抹の寂しさと解放感とが混ざって複雑だ。結句の「もう振り向くな」は、今日までとは違う明日に向かって自己を勇気づける言葉でもある。次の歌から、作者が助産師であることがわかる。新しい命の生まれる現場に立ち会ってきた一人として、若い妊婦を前に話す言葉も説得力があるだろう。「置きみやげとして」がほのぼのとユーモラスだ。この言語感覚は、作者の歌の大きな特質の一つといえる。
二十年間母と妻との愚痴ばかり吸ひこみ夫は肥満となりぬ
夫婦してコレステロール値やや高し似たもの同士と言はれたくない
切られたる西瓜は真つ赤な大口あけ冷蔵庫内を占拠してをり
姑と妻と夫の同居家族では、夫は母と妻からの愚痴を聞かされて身の置き所もないだろう。夫の肥満体形も、二人からの愚痴を吸い込んだ結果、という見方がおもしろい。似た者夫婦というのは、性質や趣味が似ている二人だが、コレステロール値の高さが同じまで広げていくところに、可笑しみが湧く。そういう表現の妙味は、半分に切られた西瓜の歌の「真つ赤な大口あけ冷蔵庫内を占拠してをり」にもあり、西瓜の自己主張と存在感がユーモラスに伝わってくる。その言語感覚の後ろには、次の歌にあるような繊細なやさしさがあふれている。
霙降る青空市のキャベツ玉春をふんはり巻き込みてゐむ
どうしてと吾子の寝息に問うてみむ青きトマトの匂ひする部屋
川原に咲く目立たぬ花のように
吉村久子歌集『風草のうた』
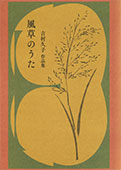
作歌力の旺盛な著者である。宮崎大学の公開講座で短歌に関心を抱いた著者は牧水の生家を訪れ、「年間一千首詠みます」と誓い、先ず四、五年はそれを実践した。
その後も十三年間に六冊の歌集を出版。本歌集はその六冊の歌集と新聞歌壇入選歌、結社誌「塔」掲載歌から一三七五首を選んで一冊に纏めたものである。
部立ては集名に因んで、「薺」や「捩花」「狗尾草」など、「地味に田舎道に生えている」(「あとがき」)草花をもって、十四に分けられている。
ガリヴアとなりて屈みぬ川原に咲きひろがれるニハセキシヤウに
草花の咲く川原の堤を人々が行き交うように、著者の上にもさまざまな日々が流れていった。子供達の成長、孫誕生、義母の介護と死、母との訣れ、自らの病気、夫の難聴、愛犬との生活と死といったそれらが、四季の花々とともに語られて行く。
あれまあと幼のごとく百八の義母の汚せる臀を拭く
明日は発つ娘が土を被せたり春めける庭に植ゑるパンジー
葬式はどうなるのかと意識すでに濁れる母が譫言(うはごと)をいふ
草花や庭の蟹にも遍く注ぐ著者の愛は、姑の世話の場面でも明るく穏やかである。歌集全体に流れる優しさ・安らぎは、著者の人柄そのものであろう。
今、傘寿を迎えた著者は、お互いに労わり合いながら夫君との静かな生活を楽しんでいるようである。
三度ほど肩をすぼめて夫に示す「寒い寒い」がききとれぬから
最後に、著者の誇りとしている新聞歌壇入選歌より。
殊更にしあはせなのねと言つてみる話題を他に変へてみたくて (東直子選)
現実のなかに遠い〈時〉を見る
岩野伸子歌集『霧と青鷺』

はるかなる〈時〉から戻つてきたやうなアオサギ一羽 川霧の中
坂の上の霧の中よりあらはれしヒトのかたちはたちまちに消ゆ
歌集の題になったアオサギが詠われている作品である。川霧の中にじっと動かない一羽のアオサギの姿は、時間のはるか向こうからやってきた誰かの化身かもしれない、と思う。深い霧のなかでは、一メートル先も視界がきかない。人の形がぼんやり現れては消える。何処から来た誰だろうか、霧もアオサギも作者の思いを揺さぶり彼方へ誘う。
どのやうな少女でありしか少女期の母と縄跳びなどしてみたし
作品にはお母様が亡くなられた歌や、母の残した手紙を読む歌があり、いつまでも母の俤は娘の記憶に鮮明に残っている。少女期の母と縄跳びをしてみたいという願望は、母と娘が同年齢になることなど、絶対に不可能で、それが娘の切実な心情を物語る。いい歌だと思う。
一本の鉄骨があり鉄の中もまた鉄にしてひんやりとせる
どこに行くあてもなけれど歩きをり手提げに春の光を入れて
太陽と月がうきゐるゆふそらはみづうみの色 この世から見る
鉄工所経営に携わっていた作者ならではの鉄骨の歌。鉄という金属の属性にふれて身体に繋がる。春の光を入れた手提げをもって当てもなく歩くことも、夕暮れの空に太陽と月の両方を見るのも、異界の出来事のような世界だ。作者は「この世から見る」と、こちら側にいることを確認するが、作者の視線は、時々、現実のなかに遠い〈時〉を見る。第二歌集になる。
日常という虹の切れはし
向山文昭歌集『ディーゼルの列車』

第一歌集『反射率7%』から十年後の第二歌集になる。妻や娘、義母、孫など家族の歌と身辺の出来事など、日常の生活圏の出来事が歌の素材になっている。
夕暮れの犬が行きたい方向に消え残りいる虹の切れはし
家中に自ら挿した水仙を誰かが飾ってくれたのだと言う
もう記憶できない義母とまだ覚えられない幼を一緒に写す
巻頭におかれた連作「虹の切れはし」の中の歌。犬も家族の一員で、この犬も病で命を終える。二首目の水仙を飾ったことを覚えていない、呆けていく義母と生まれたての幼子の様子は、その都度、歌に詠まれて、義母は死を迎え、幼子は成長する。何処にでもある日常生活。そこにはごく普通に、それぞれの生と死があり、希望と亡失の日々があり、空の虹が徐々に薄れていく様に似て、虹の切れはしは、私達の日常の象徴ともいえる。
仏壇が好きな幼か知らぬまに火なき線香数多に刺さる
ふんだんにセロテープ使い幼子は今日も何かをつないでおりぬ
何にでも興味を示す幼子の微笑ましい様子が描かれている。しかし、仏壇の沢山の線香と際限ないセロテープの使用は、終わりと、明日へつなぐ行為のメタファとして、作者の思念がさりげなく示されているだろう。
蕎麦の芽が一斉に伸ぶ 地球をすこし持ち上ぐるかに
水平に林を抜けて来し夕陽コスモスの花の八角を射す
ふらふらと折れ線グラフのようにゆく雪の気配の枯野の黄蝶
これらの歌の、蕎麦の芽の伸びが地球を持ち上げるような感覚、水平に林を抜けてくる夕陽、コスモスの花の八角を射すという描写、黄蝶の飛び方に「折れ線グラフのようにゆく」という表現など、物理学的な視線は魅力的である。
「和」のバロック
金澤照子歌集『風にまぎれて』

著者三十九年ぶりの第二歌集。著者は八十代半ば、あとがきにある塚本邦雄、玲瓏とくれば、われらが「塔」東海歌会の故、早崎ふき子氏が思い浮かぶ。写実から抽象に飛ぶような作風は同じだが、一番の違いは、早崎の「洋」に比べ、「和」のイメージが強い。いわば「和」のバロックというところか。目次を見ても、連の題はすべて二文字の漢字で統一されていて、塚本の影響を感じさせる。また、作品は鋭敏な感性に満ちている。
われのため佇てる男を雑沓にかくし絵のごと透かし見てゐつ
妻ならばいかに惚れぼれ仰ぎ見む屋根葺く男の迅く無駄なき
「男」という突き放した言い方で対象との距離を敢えて取る。一首目、恋人かそれ未満か。試すようにひっそり見ている。二首目は「妻ならば」という前提だが、もちろん我も、なのだろう。
雛の呼吸(いき)やよひの夜をしめらせて塩のごと重し古き家族(うから)ら
ひととせの暗(やみ)よりいでし古雛らそれぞれちさき唇(くち)をあけたり
雛を詠んだ二首。雛は古い家族制度の象徴か。二首それぞれのルビに思いが載っている。一首目「塩のごと重し」塩は生きるのに必要不可欠なのであるが。二首目、一年ぶりに雛たちは「ちさき唇」をあけて呼吸する。その息が聞こえるようだ。
百合の蕊に染められし掌(て)を洗ひゐる誰の伝言ぞなかなか消えぬ
他愛なき嘘かも知れぬ秋の掌(て)に君が残しし言葉ひとひら
「掌」を詠んだ二首。掌に「伝言」や「嘘」が残ると。言葉について独特の感覚だが妙に納得させる。最後に好きな歌二首だけ。
わがのみし湯呑ひとつを洗ひゐてまこと小さき暗(やみ)を伏せおく
うすもののブラウス一枚濯ぎゐて花柄ひとつ手より逃しし
いい感じの風
相原かろ歌集『浜竹』

相原かろさんは、私と同じ結社「塔」に属している。私は前からかろさんの歌のファンで、塔誌が来たら必ず読む歌人の一人である。読んだらたいてい、くすっと笑う。そして時にうなずく。
この度歌集が出たというので、喜んで読んだ。おもしろかった。さて、評を書くということで、モチーフのようなものを探してみたのだが、この歌集には、それがほとんど見つけられなかった。
くっついた餃子と餃子をはがすとき皮が破れるほうの餃子だ
吊り革を両手で握りうつむいて祈る姿で祈らずなにも
ネクタイは柄の不思議よゾウリムシみたいなやつがむらむら並ぶ
踏切の前で止まっている母を電車の中から見て通過した
どの冬の道にもあった手袋は落ちていますという姿して
脳天は晒されやすし下りゆくエスカレーター大江戸線の
これらの歌はどれも、だれにも覚えがあるがなかなか短歌にしないところを掬い取って、読む人に気づきを与える。読者は、それを楽しみ、さて、と次の一首を楽しむ。何回か読んでいくうち、それでいいのではと思えてきた。後記によると、『浜竹』は、作者の祖父母の住所の地名で、「特にこれといった風景や名所があるわけではない」そうだ。歌の中に、それを歌集の題にする作者の意図と、同時にやはり後記にある「いい感じの風」を感じた。
モチーフのようなものは見つからない代わりに連の題には仕掛けがあって、先に挙げた四首目の歌と同じ連に、次の歌がある。
日曜のフードコートに飯を食う家族の単位単位に酔いぬ
この連の題は「踏切の単位」という。探してみると、この方法で、すべての連の六~七割が作られていて、それを探していくのも、この歌集を読む楽しみになったのである。歌集の読み方ということを考えさせられた、個性的な歌集だった。
老いゆくは
後久昇歌集『白木蓮』

後久昇さんは、私と同じ名古屋市にお住まいで、超結社の「中部日本歌人会」の会員である。だからお名前は存じ上げているが、まだちゃんとお目にかかったことはない。一般に歌集には、著者のお人柄が表れるという。お会いする気持ちで、歌集を読んだ。
ほころびたる白木蓮を見上ぐれば真白き花に霊気ただよう
御無沙汰の納骨壇に読経せる僧の背後に両親の顕(た)つ
まず冒頭に歌集の題である木蓮の歌が並ぶ。木蓮の花に霊的なものを感じる作者は、二首目のように父祖の霊にも敏感なようだ。
愚痴を聞くことも勤めよ古新聞妻としばりぬ回収の朝
瀬戸線の赤き電車は引退す通勤の日日重ね見ている
八十代、二つの会社を勤め上げ、静かに暮らす作者は、妻に優しく、目に入るものに自らの思いを重ね生きている。
電灯を消してひととき安らげり己と向き合う色なき世界
サウンドに餓えたる吾はこの夜更けダイヤル廻し旋律さがす
また、一人のときは、己と向き合い、自省し、時にラジオなどの音楽に耳を傾けることを、楽しみとしておられるらしい。
朝光が玄関ドアの格子くぐり幾何学模様を床に置きいる
胃カメラの一つ目小僧口に入り咽の曲り角今通りおり
この二首には現実を詠いながら、擬人法がうまく取り入れられていて、楽しい。二首目は胃カメラを飲んでいる場面なのだが。
沈黙は立派な会話と人言えり眉間のしわが困苦を語る
老いゆくは成熟すること老医のことば残生にても夢は生まれるか
時々箴言のようなものが歌の中に表れて、それを咀嚼して自分の世界を作っている作者である。まじめなお人柄が感じられる。二首目は疑問で終わっているが、決意であろう。さらなる夢に向かう作者に敬意とエールを送りたい。
フェアな視点から
松木秀歌集『色の濃い川』

『色の濃い川』は、松木秀さんの第四歌集になる。松木さんといえば、風刺に富んだ切れ味抜群の社会詠をイメージする人も多いだろう。第一歌集『5メートルほどの果てしなさ』収録の〈新聞も読んでない今日まあいいか明日には明日の殺人が来る〉のような歌に、かつてとても衝撃を受けたのを覚えている。
どんなものにも適切なサイズありたとえば愛国心などにも
「空爆」という言葉など使うとき爆撃側の立場に立つも
本歌集にも、例えばこれらの歌のような、現代社会に鋭く切り込んでいく歌はもちろん収録されている。とはいえ、第一歌集から第二、第三と時間を経るごとに顕在化してきた北海道に暮らす自身の日常の中での気づきや発見を詠う、というスタンスに今回の歌集はより一層力点が置かれていて、松木さんの四冊の歌集の中では最もマイルドな読み味になっている。
北海道以外気温がみな赤いアメダス見つつ麦茶飲みたり
「東京に生まれてくるのも才能」と言いし人ありわれもしかおもう
北海道の歌を引いてみる。一首目、猛烈な暑さの他の地域を高みの見物、とでもいった調子だけれど、北海道だけ色が違うということに対して、かすかな疎外感もあるのかもしれない。二首目、生まれも育ちも北海道の作者による、字余りしながらの「われもしかおもう」には、並々ならぬ説得力がある。
深夜には健康グッズのCMをやっているけど観るよりは寝ろ
飲み会でからあげばかり食う人がひとりふたりは絶対にいる
これらの歌の面白さは、わざわざ説明する必要もないだろう。日常を題材とし、確かな観察力と卓抜したユーモア感覚を自在に操りながら次々と繰り出される歌を、読み手は存分に楽しめばよい。
台風の接近の中ひとりにて台風も一度の命とおもう
歌詞を全部覚えてないと口パクはできないゆえに少しはえらい
これまでは風刺や皮肉にともすれば覆い隠されがちだった松木さんの素顔が、このような歌から垣間見えたような気がした。一首目、各地に被害をもたらす台風を、有限の生を持つという点において、自分と等価な存在だと捉えてみる。二首目、歌手の口パクが明るみになれば非難が殺到するのは免れないけれど、それを全否定はせず、歌詞を全部覚えて口パクが出来るようになるまでは努力した、という事実の存在を見逃さない。あらゆる物事に対してきわめてフェアな視点に立つことで、本質を射抜こうとする姿勢がこれらの歌にはある。この姿勢は実は、松木さん元来の風刺や皮肉と根っこの部分は同じものなのだ。
故郷に抱かれて
池本俊六歌集『赤き故郷』

真っ赤な意表を突いた表紙に著者の故郷に対する熱い思いが集約されているのだろう。次のような歌がある。
東方の山の上なる茜雲里をまっかに我を染めくる
青竹を腰に差し込みガキ大将あだ名は「蝮(は)め六」おいらの事さ
故郷の野原を走り回った少年期のまさに面目躍如たる姿がここにある。しかし長ずるに及んでは櫨谷の由緒ある氏神の総代として、阪神淡路大震災からの復興に尽力されている。推古天皇十一年櫨谷庄内氏神として勧請、江戸時代には「妙見神社」また、「妙見宮」と呼ばれた福谷村の産神で東西百間に南北百二十間の広大な境内を持つ社と記録されている。
総代も大麻の帯を襷がけ神代界に入りゆく心地
義経の本陣構えし言い伝え残る神社の弓引き神事
天狗なく祭りは出来ぬと言い伝えその大役に胸張り我は
様々な由緒と神事の記録の歌も興味深い。古来、大麻は神事になくてはならない植物だった。
諸子らの泳ぐ姿を見つけたる未だ薄(うす)ら氷(ひ)を残す小川に
採り残したる大根が花咲かすこの白色も畑の景色
笹藪のあちら此方に獣道小川へつづく足跡のある
時代の趨勢で都市化宅地化の波が押し寄せてきているようだが著者の住む櫨谷町には未だ少しの猶予があるようだ。豊かな田園風景が広がり、まさに「うさぎ追いしかの山 こぶな釣りしかの川」の叙情が残っている中で農事にいそしむ姿が素直なストレートな言葉で詠われている。
ゆったりと気流をまとい鳶一羽ネギ植付けの我を眺める
亡き父母のやさしさに似て微かなる瞬きみせる冬空の星
このような世界を失ってしまった同世代の筆者としては限りない羨望と、懐かしさを感じつつささやかな評を閉じたい。
空想と現実のはざまで
金近敦子歌集『東から西に』
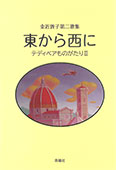
目次を見るとはじめのプロローグと終章のエピローグとがあり歌集全体が一つの意図を持って編まれているようだ。
最近の君つくりこみすぎてる 自然を詠めよと夫のひとこと
こんな歌も集中にあって空想と現実の区別は必要かと問われれば必要はないのだけれど、そんなことも視野において評を進めてみたい。
七階の喫茶室より見る夜景 今宵は何故か涙に滲んで
洞のうち闇に漏れくる秋の陽に貪るやうに眠れる蝸牛
ポップな感じの場面設定、都市叙情ともいえる若やいだ軽やかさが「涙」をセーブしている。蝸牛の歌はどこか象徴的だ。命へのそこはかとない畏敬の念をいだかせる。
ヒロシマの炎天に在りし深き静寂… 蝉も死に絶え影も燃え尽きて
橋近く瀕死の人々余りに多くて十六才の父は妹を捜し難くて
されど父は六十数年散華やめざりき ドームの見ゆる橋の傍にて
「ヒロシマ」と表記すればこれは原爆関連の事となる。やはり身近な被爆体験を持つ人にとっては軽視して通り過ることの出来ないテーマなのだ。特に著者の父君からの直接の聞き伝えなればなおさらのことだ。七十余年経過した今でもある種の生々しい体感が伝わってくる。。
きみの描くなないろの雲の間を自由に飛び行く複葉機ひかる
そんな吾も惹かれし百年前の旅アルトゥーロ・フェラリンの複葉機の旅
葉桜の季節を過ぎて五月末パイロットテディと飛ばむ中天
この辺の歌は作者の最も得意とする分野かも知れない。ノンフィクションとメルヘンのない交ぜになった時空を自在に飛び回っている感じだ。取り上げるべき歌を多く残してしまった。
違うところを見ている人
上澄眠歌集『苺の心臓』

この作者は、普通とは違うところを見ている。見つけてしまう。その感覚を読者にゆるいスピードで投げかけてくる。
歯がいっぱい入っていると思ったら全部ちぎれた消しゴムだった
点滴を受けるみたいにイヤホンを耳にさしこみじっとしている
歯がたくさん入っている袋はもちろん恐ろしいが、ちぎれた消しゴムがたくさん入っている袋だって恐ろしいよと思う。イヤホンを耳にさすのは好きな音楽を聴くため。楽しげな場面であっていいはずなのに「点滴」が不穏さを醸す。
カマキリのたまごくらいにたっぷりと泡立てなさい洗顔石鹸
蟻でいえば触覚が生えているところ爪に力を入れ掻いている
一本ずつ洗っておりぬ自らのもと前足ともと後ろ足
動物や昆虫が出てくる歌にも妖しさが隠れている。カマキリのたまごは、それ自体は愛らしい形だが、ひとたび孵れば大変なことになる。自分を蟻に喩えて卑下するわけではなく、単に頭を掻くときに、蟻を感じているという不思議さ。三首目は浴室での場面だが「もと前足ともと後ろ足」の認識にたじろぐ。
ハイブリッド!ハイブリッド!と音をたてあなたが鼻をかんでおります
傘をさすまでもない雨 顔にあたるこの感じ微微微微微炭酸
パートナーのくしゃみの場面。降りかかる小糠雨。どれも現代的な比喩で楽しいが、ハイブリッドとは何かと改めて辞書を開いてみれば「異なる種類・品種の動物・植物を人工的にかけ合わせてできた交雑種」とあり、とたんに笑みが消えてゆく。
世界の現在と過去を見つめる
金井一夫歌集『海外詠』

平成十二年〜三十年末(著者64〜82歳)までの約十九年間の、海外旅行詠だけを纏めた作品集である。世界地図を前に著者の訪れた国と都市をたどりながら、その多さに驚くばかりである。まさに地球規模の世界旅行である。
アマゾンの蝶が天より溢れ来てあたりたちまち光のしぐれ
アマゾンの雄大な景を背景にした、無数の蝶の翅の返す光と、澄明な空気感が印象的である。神秘的で、神の啓示を思わせる。
生きもののように蠢くオーロラの光、ハバロフスクの空港で見た幻日、ヒマラヤの山小屋を包む霧、これらはすべて感動的な光景であったろう。しかし、著者の心を動かしたものは自然の美しさだけではない。
女らはうつむき加減に歩み来てアミーゴと笑ふタキーレ島にて (チチカカ湖)
セラ寺の問答実践見て居れば若き僧らはわれを意識す (チベット)
女性達のはにかんだような仕草や、「若き僧ら」の様子に親しみを感じる著者の人間観察には、温かな眼差しがある
枯葉剤、戦争証跡博物館、先天性異常、流産死産 (ベトナム)
真向ひの道をはさみて殺し合ふそれが内戦とセルビア人言ふ (サラエボ)
戦争証跡博物館前に佇む子どもに、枯葉剤の恐ろしさを見せつけられ、サラエボの民家の壁に残る銃弾の痕に、ボスニア、ヘルツェゴビナ紛争の凄絶さを思い言葉を失う。四十三ヶ月間にわたる内戦で二十万人が亡くなり、二百万人が難民となって逃れていった。ほんの二十五年前の出来事である。
著者は人間の犯した歴史の負の部分からも目を逸らさず、歌によって人々に伝えようとしている。訪れたものの使命として。
過ぎゆけば善しと思えること多し
嶋寺洋子歌集『父のキャンバス』

父の描きしキャンバス百余残りをり時折並べる画廊のやうに
著者の父の油絵がカバーを飾る本歌集は、湖国に生まれ湖国で生きる著者の、家族アルバムのような一冊である。
前半のⅠ章は少女時代の思い出から、結婚、子育て、夫の退職までを、Ⅱ章は年老いた父母や姑の生活ぶりと介護を主な内容として編まれている。教職にあった夫同様、著者も女子高校の教員として十年間勤めたというが、そうした仕事や海外旅行の歌などはほとんど収められていない。著者にとって大切なのは実家の両親であり、湖国の姑、幼い孫たちを含む「家族」のことなのである。
寡黙なる父との会話につづきありメールの画面に文語文来る
少しだけ強がりやめてと義母に言ふ介護認定受くるとふ朝
母を叱り姑をなだむるこの日頃 死にたいなんてもう言はないで
湖岸の町北国町(大津市)で洋服店を営んでいた父、浅井家の居城小谷城趾のある浅井(長浜市)に一人住む姑は、「憂いことやのう」と労りの言葉を掛けてくれる人であった。
猫の名を付けられわれはトムばあちやんトムぢいちやんと仲良くくらす
二人の仲の良さはまるで恋人同士のようである。
とりたてて話題は無きに運転の夫に声かく穂薄ゆるると
『閑吟集』の歌が思い出される。
あまり言葉のかけたさに あれ見さいなう 空行く雲の早さよ
幸せな人生とは、日々を豊かに送ることのできる人の事であることを、本歌集を読みながら感じたことである。
生き方選び
森尻理恵歌集『虹の表紙』

「塔」所属の地球物理学研究職の著者の第三歌集。一人息子の確かな成長と、闘病生活の十一年間がリアルに読み手に迫ってくる。内容は重いが暗くはない。たんたんと事実を具体的に積み上げて、奥行きのある哀感のひびく集である。
わらわらとバスより降りる人の波がんセンターに入りゆきたり
薬選びは生き方選びかとりあえず普通に仕事がしたいと言えり
体重と体温を毎日測れとぞ虹の表紙のノート渡さる
率直な医師の言葉に頷きし息子は部屋出て「重いな」と言う
近い先のことのみ考えゆく暮らしこれから始まる いつまでか知らず
三部構成の二部は一首目から始まる。「バス」の具体が効果的で「がん」の平かな表記も、端的な結句にも、歌に対する美意識があり、ストイックなまでの表現が心を打つ。二、三首目は生き方選びに連動しており、「重いな」の息子の一言に病の実状がわかる。五首目には先の見えない不安感が詰まっている。
「がんばった」は他人から言って貰うもの自分から出す言葉ではない
生きることすべてが修業と言われしと子の思春期に良き出会いあり
「自分から出す言葉ではない」と言えるからこそ、「良き出会い」と捉えることができ、母と一人息子の心の繋がりがわかる。引きたい歌は数限りなくあるが二首を引く。
やわらかい風を選んでしゃぼん玉を冬の日差しの中へと送る
少しずつ眉毛とまつ毛の戻りきて見覚えのある顔となりゆく
丁寧な眼差しの描写
川野並子歌集『綯い交ぜのみどり』

「好日」入社十五年を区切りに、「好日賞」を含む、四百七十七首を収める第一歌集。真如町に住む著者の日常は真如堂の四季と呼応した作品も多く、丁寧な描写は絵画のようだ。
真如堂境内東の小堂に千体地蔵の座す薄ら闇
今年また藤袴咲く真如堂西の砂利道おなじところに
前者の「東の小堂」後者の「西の砂利道おなじところに」など、何でもない所だが、この具体的表現が歌の景を鮮明にしている。こうした表現力は色彩感覚にも通じているようだ。
卵色カーテンのなか検査待つたまごの殻に守られながら
夏去りて南天の実は青年の失意のような錆色をなす
病室のカーテンの「たまご色」は確かにと納得し、下の句への展開が穏やかでありつつ個性的だ。後者も「青年の失意のような錆色」に高い独自性があり、「青年の」が効いている。父の挽歌をはじめ、家族それぞれの歌も折折の様子を伝えている。なかんずく亡き母の歌が胸をうつ。
天井の低き二階に臥す母は達磨の色紙を見つめていたり
母臥せる竹のベッドのきしむ音六十年経てなお耳にあり
「達磨の色紙」に時代性があり「ベッドのきしむ音」が切ない。こうした身めぐりを核にした集中、最も印象深かった一連が「青虫」である。著者の歌の師、神谷佳子「序」の言葉を借りると、「大きく言えば神羅万象にひそむ生命継続の志」を匂わせて、青虫の命も、著者を含めた人間も命あるものすべてが生きて輝いている。
右へ噛み前へ進んで左へと葉を食む青虫ひたすらに食む
後ろ身に力を入れてぬぬうっと前へせりだす青虫の歩は
梔子の若葉を離れぬ青虫を剥がせばくるりと弾む柔肌
補助輪のない自転車に乗れたよと幼子弾む青虫歩む
この星の大気圏とう薄膜に覆われて棲む青虫われも
つぶさに見る
上田善朗歌集『鯖街道』

四百六十六首を収める第三歌集。郷土若狭を丁寧にうたう。
お水送り終はりし若狭の里の春各駅停車のやうにやつて来る
白砂なる若狭の浜の地引網大暑の海を引きしぼりをり
鯖街道若狭に入り来て山峡の雨が早める家々の灯火(あかり)
一首目、三月の奈良東大寺「お水取り」の香水は、若狭の「鵜の瀬」から十日間かけて二月堂の「若狭井」に届くという。若狭の春はその神事「お水送り」からスタートし、「各駅停車のやうに」時間をかけてやってくるのだ。二首目、「引きしぼりをり」に地引網の豪快さが伝わる。夏の若狭の活気ある一場面である。三首目、山峡に降る雨が辺りを暗くするため、家の灯りを早めに点す。風土と暮らしが密接に繋がっている。
百伝(ももづた)ふ敦賀とのみに干し若布買ひ叩かれる破目となりをり
立ちゐても濤屈まりても濤どうしやうもなく原発の見ゆ
若狭湾沿岸には原発が集中しているという現実もある。一首目、「百伝ふ」は角鹿(つぬが)(敦賀の古名)にかかる枕詞。干し若布が買い叩かれるのは風評被害によるものか。二首目、「どうしやうもなく」に、そこに生きる者の悔しさ、虚しさが滲む。
石垣に張りつきてゐるくちなはに舌一瞬の長さありたり
よく見れば見れば見るほど省略のゆき届きたる海鼠なりけり
小動物の歌は、観察力の鋭さに裏打ちされて味わい深い。一首目、石垣に「張りつきて」いる蛇の「舌一瞬の長さ」という把握は、じっと動かない蛇のいのちそのものを一瞬見たかのようだ。二首目、「よく見れば見れば見るほど」と対象に近づいた挙句、省略のゆき届いた「海鼠」であると感心する。まるで落語のサゲである。この、つぶさに見る作者の姿勢が、何気ない日常に、数々の発見や楽しみをもたらしているに違いない。
取り出される臓器
白石瑞紀歌集『みづのゆくへと緩慢な火』

塔短歌会所属の著者第一歌集。白い装幀に銀の箔押しで、激しい水しぶきのような、火のかけらようなものが描かれる。
アフリカの打楽器が鳴るときがあるMRI装置の中で
今回は縦に切らせてもらうねと内診しつつ担当医が言う
MRIの装置は大きな音がするらしい。「耳元で工事をしているよう」とも聞くが、作者はどこか楽しげで気分の上がる「アフリカの打楽器」を感じ取る。MRIとアフリカの取り合わせが魅力的で、ふいに動物たちが闊歩する草原へと誘われるようだ。まるで野菜や肉を扱うような「縦に切らせてもらうね」の医師の言葉。優しいけれど、切るのは臓器だ。現実は厳しい。
肉腫かもしれぬ腫瘍は子宮ごとわれから離れ検体となり
臓器ひとつどうってことないわれはまだひかる時間の真ん中にいる
灯る火のあらざる洞にわが卵はいまもひかりを運びいるらむ
臓器は作者の体から取り出され、検体となって運ばれていく。子宮が体から離れていくという感覚は、他の臓器とは違うはずだ。「どうってことない」と言いながら「灯る火のあらざる洞」と失った臓器を思う。運ばれるひかりとは、命を乗せていたかもしれない光だ。胸が苦しくなった。
すべて『竹』と契約したり葬儀にも『松竹梅』のあること知りて
いつからかどこからか死はあらわれてわれの周りをゆらゆら踊る
父の見送りも歌集の大きなテーマだ。ややユーモラスだが、手術を受けた身で葬儀の打ち合わせをする気持ちはいかばかりか。父にも、いずれ母にも、そして自分にも訪れる死を「ゆらゆら踊る」と書く。しかしそれは、案外怖くはなさそうだ。
音を聞きたい
永田愛歌集『アイのオト』
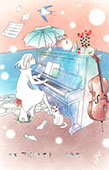
愛らしい女の子と猫、ピアノ、チェロなどが描かれた印象的な装画は歌人の千原こはぎによるもの。
タクト振りながらときおり空(くう)を見るきみのなずきの重さをおもう
四本のトロンボーンに友の音あればひとつをききわけて聴く
オーケストラに所属しているらしい作者。タイトル通り、「音」が大きなテーマになっている。ほんとうは、タクトの指示を見なくてはいけないのに、指揮者の頭の重さを思い、その人の考えていることへも作者は思いを馳せる。
ぬばたまの髪にかくれている耳が記憶している声を思えり
両方の耳まっすぐに立てて聞くきみに呼ばれるわたしの名前
相づちをあまり打たないひとといて朝の雨を言いそびれたり
こんな瑞々しい相聞歌も魅力的だ。ここでも作者は相手の「音」をよく聞いている。両の耳をぴんと立てて聞いている様子は、さながら表紙に描かれた猫のようだ。好きな人が発語する自分の名前は輝いて聞こえたに違いない。無口な相手を前に、自らも無口になってしまう、合わせ鏡のような関係性が眩しい。
冬の日にわれとふたりで生まれ来しいもうとがいて墓に眠れり
お墓から家が見えるということもうれしく家の方をながめる
生まれることができなかった双子の妹。彼女の存在は作者に枷のようについてまわる。互いに分身であるから、妹の墓はいつか、自分の墓にもなるだろう予感が漂う。けれど、そこには安住の地を見つけているような心やすさもあるのだ。
生きる姿勢として
石本照子歌集『山法師』
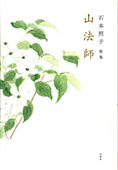
「あとがき」によれば九二歳という数字があった。もとより著者のことは歌集を読む範囲以外のことは知らない。日常の営みの中から紡ぎ出される叙情と、ある種、年齢に対する覚悟のようなものを受け止めてみたいと思った。
比叡山に影落しいたる大き雲ながれ来るなり加茂川堤
川下の古き社に初詣でたき火の跡あり神事(まつり)はすみて
うす曇る春のベンチにはずされし手袋残り山朱萸の咲く
くれないの光に映えて里山の稜線しばしふくらむ夕べ
叙景の中にある叙情を十分にすくい取ってそこはかとない広がりを見せている。雄大な雲の流れ、たき火の跡の静謐、手袋の現実感、ふくらむ稜線、など格の高い描写だと思う。
使い慣れし針箱の中の道具たち目打ちは祖母の使いいしもの
肉親に繋がる記憶は抑制された言葉で語られている。
買い換えし冷蔵庫の白き照明にはにかむ如しリンゴ半分
下の句が意表を突いて巧みだ。この様な歌は集中いくつか見られたが誌面の都合でこれだけを取り出した。
昼の陽に照らされているあの山の木の下に空気のようにわたしは
誰かの事と思い居りしが週五日の夕食宅配申し込みたり
髪の毛のように記憶がぬけ落ちるそういう自分とつき合い生きる
生きる姿勢として「空気のように」はなかなか至り得ない境地だ。しかも明るく清明で温かい。筆者も可能ならばそこの近くにまでは寄ってみたい気がする。宅配の夕食、家事の軽減にはなるだろう。自分を見つめありのままを受け止める姿勢。
重なり合える雲の切れ間にほっかりとあきたる小窓おや、青き空
もう一首。なんとも若々しい感覚と表現に賞賛をおくりたい。
菩薩の功徳
佐古良男歌集『念彼猫力(ねんぴにゃんこりき)』

このユニークなタイトルは観音経の「念彼観音力」をもじって「ねんぴにゃんこりき」と読む。「日本歌人」所属の第四歌集。作者の飼う猫は家族以上の存在、時に神のようにも崇めている。
猫の目は暗がりのなか生きてゐる闇こそ神の坐すべきところ
後朝の別れならねどわが耳を猫の和毛が撫でて去りゆく
夫婦仲くづれかければ分けて入りニャアとし鳴けば念彼猫力(ねんぴにやんこりき)
奈良の談山神社で長く神職に就いていたという作者の歌は、古今東西多岐にわたり、軽やかに言葉が紡がれているが、根底には初老の男の諦念や焦燥が見え隠れする。
尖りたる犬歯を医師に削られぬ心にさやるものの始末は
たちあがる力をすでにうしなひて池のおもての半月や鋭し
俯せに道に倒れしわが影を桜吹雪が華やぎくるる
このまなざしは、おのれ自身から国家のありようや歴史にまで広がってゆき、じりじりとした怒りやひりひりとした悲しみを諧謔まじりに伝えてくる。
家も名もこの惑星に遺すべきものならなくに朝焼けにたつ
阿弖流為やフセインなどにおよばねどやや怨霊化しつつわがあり
かなしみをあらはすことばみつからず樹の魂に抱きついてみる
愛猫は先立ったが作者には菩薩とも呼ぶべき妻が傍らにいる。
やがて妻がおもひで語る通夜の席われはいかなる男であるか
まどゐにはつねに猫ありつまのありここがまことのやまとまほろば
死は生を輝かせる
ダンバー悦子歌集『ふた束の水仙』

この歌集には詞書がない。歌だけを見て下さいという作者の気概の表れなのだろう。「塔」所属の作者の生活の場はニューヨーク、夫と娘と三人暮しのようだ。
米国人の夫の部屋より流れ来る違和感を超えて宮城道雄が
飯をタタクと夫言えば飯を炊くでしょうと娘の直しに厨が火照る
憧れの亭主関白とう言葉秘めて主人の振る舞い柔らか
宮城道雄、飯を炊く、亭主関白、日本人にとっても既に懐かしい。都市の風物も四季を通じて様々に詠われている。
桜祭りに花笠音頭を踊る人募集している広き植物園
噴水の向こうに黄色い花が見え夕菅と気づくまでの数秒
現代の都市暮しはどこもそれほど変わりはないだろうが、十九年前恐ろしいテロがあり、多様な人種がひしめいている世界最大の都市である。歌のなかに〈影〉がよくみられるのも緊張感や違和感の表れなのだろう。
満員の席にポツリと空席があり影のみが座しているなり
柔軟に伸び縮みする影纏う我に見知らぬ冬の近づく
この瞬間爆破されたらと思うこと習慣になる地下駅構内
人々の背負いゆく神に人種あれば言の葉ちがい善悪もちがい
父母の葬儀や法要に伴い日本の故郷に帰省する歌も多くあり、歌集に奥行きが生まれている。また歌集も終わりになるころ読者には唐突に思えるように夫の死が詠われている。
寡黙なりし主人の逝きて娘とふたり連翹満開ぼーっと見ている
黄昏に濃きところあり君の背を見つけて走る秋のはじまり
異国に棲む孤独と向き合いながら、歌の世界はより深々と極まっていくに違いない。第二歌集を期待したい。
野の花のように強く
平田洋子歌集『穏やかな空』

歌集を手にしたとき、おとなしいタイトルだと思ったのだが、タイトルに籠められている作者の切実な気持ちが歌集の序盤で分かり、納得させられた。夫の長年にわたるDVに苦しみ、遂に子供たちを連れて家を出て行くまでが序盤である。
君は支配者われは隷属と思ふとき崩れゆきたり二人の和音
長き苦悩のすゑに定まりしわが心出奔の朝をしづかに迎ふ
「こつちへお出で」と手をのべ給ふ師の家へ向かひぬ歳晩の穏やかな空
夫の許を去った作者は、職を求め暮しの算段に懸命になりながらも心はすこしずつ平穏になっていった。だがその矢先、唯一の理解者だった弟を日航機の墜落事故で失ってしまったのだ。
わが離婚恐れるなと励ましてくれし弟ふいに逝きたり
原生の木木におほはるる細き道を死者のみ霊に導かれゆく
標的にされたかのように人生の不幸、不運に甚振(いたぶ)られながら、それをしなやかにはねのける強さを作者は持っている。子供を守る母の強さでもある。
DVの悲しみを盛る器とし短歌はわれに差し出されしか
季(とき)くれば可憐に咲ける野の花のやうにありたしわれの一生(ひとよ)も
「深い悲しみは言葉にしなければ、人はそれを越えてゆけないのかもしれない」と後書きにも書かれているように、試練を言葉に置き換えながら生きてこられた。悲しい歌が多いが、その間にも身辺の自然を見つめる歌も多くあり、作歌が作者の糧になっていることがよく分かる。
興福寺の側溝に入り涼をとる鹿が汗ふくわれを見てゐる
ナースらと卓を囲みてDVの早期発見のプログラム練る
穏やかな晩年を手に入れた作者だが、自身の体験を社会に役立てたいという熱い思いはこれからも変わらず続いていくだろう。「白珠」所属の作者の第一歌集。
衣(きぬ)を脱ぐように
福士りか歌集『サント・ネージュ』

土地に育まれた言葉があるように、そこに生きる人々の皮膚に沁み込んでいる風景がある。それを作品に描くとき、ほのかな息づきとなって味わい深い世界がひらく。
冬の陽に圧さるるごとく沈みゆき層をなしたり道の辺の雪
積む雪の底ひに湖(うみ)のあるごとく青く灯れり錐寒(きりさむ)の朝
三月の雪はしづくを抱いて降る林檎の幹をあかく濡らして
北国の雪とひと言で言い切れない表情がある。積もった雪が陽に溶け寒さに固まりを繰り返して層をなす道の辺の雪。青みを帯びた静かな湖の広がりを底に湛える寒い朝に積っている新雪。林檎の幹にやさしい栄養分となる雫を抱き降る春の雪。
それぞれの雪の底に抱えるものをじっと見つめる作者がいる。
海沿ひの村に生まれきサワサワと胸底に波の音をたづさふ
縁側で猫を抱きつつおほははの百年動きし心臓おもふ
渓流に魚の影をさがすごと英語聞きをりカナダ二日目
胸の底にさわだつ波音は、海沿いの村で生まれ携えてきたものであることに気づく。抱いた猫の心音を手のひらに受けて、百年脈々と生きた祖母の心臓へ思いを馳せる。流暢な英語から言葉を捉えることを、渓流の底の魚影をさがすことに重ねる。
生きるものの胸の奥に触れ、ものの底を探るとき、そこから広がってゆく空間がある。
水を恋ひ水を見に行く田植ゑまで少し間のある大潟村へ
大寒の雪雲ひらき青い鳥群れ飛ぶやうな晴れ間ひろがる
寒気すこしやはらぐ冬の中空に裸身をさらす月の明るさ
見に行く水の広がりは、私たちの主食であるお米が稔るところ、田植え前の代田。生命を育む準備が整った場所だ。寒さの真っただ中どんよりと厚い雲がひらくと、その晴れ間はことに眩しい。そこに生の力が漲る青い鳥を見る。冷たい空気が和らぐ冬空に月が明るい、そのままをさらした凛とした姿がある。
もののなかに、見えない力、生命力のあるものが潜んでいることを感じ取っている。
降る闇と湧く闇ありて水の辺に延びる桜のしろがね凝る
触れさうで触れぬ指さき 水際の桜はあをき光をまとふ
この雨は明日のひかりに続く雨つつじは衣(きぬ)を脱ぐやうに散る
大風にポプラなびいてゐるやうでじつと動かぬ枝のなかほど
水辺から闇の中に平面に広がる桜は積った雪に固まり、水際の桜は青い光を纏い、作者にとって不安定な場にも動じない。明日の光に続く雨に躑躅は花びらをするりと脱ぎ落し、大風にポプラの枝の中程は動かない。
何かを脱ぎ捨てて明日の光へ届くように、「聖なる雪」の輝きに近づくために言葉に真向かう時が静かに流れている歌集だ。
人生と心情と思惟との一体化
筒井早苗歌集『椿は咲きて』

「新月」代表として、二〇一八年末に終刊を果たした著者の第七歌集である。一九五四年「新月」入会より歌との長い歴史と深い思いが凝縮されている。著者自らの人生と心情と思惟とが一体化し、老いの一人居の現場が鮮明に立ち上がる。
哀歓のおぼろおぼろと雨が降る現世前世のけぢめもなくに
かき曇りゆらゆら低く黒揚羽呪文をまきて消えてゆきたり
日光に月光菩薩を脇侍とし薬師如来に老いはきまさず
いずれにも著者独自の感性と個性が光っている。「現世前世」「呪文」なども言葉の持つ印象とは違い不思議な明るさがある。
人恋ふる心忘れて久しきよ人恋ふはよし山上の虹
生かされて加速してゆく一年の良きも悪しきもすでに茫茫
花のなき年もまたよしあぢさゐの青葉ばかりが風をよびゐる
五色椿の五色(いついろ)まなこに収めきて仄めく胸や夜(よる)ふけてなほ
生かされている認識は老いの故でなく、自己省察と自らの人生観死生観に通じている。自由自在に詠いながら、一首目や五色椿には瑞々しい艶やかさがあり、次の帯の歌にも通じている。
覚悟などあるもあらぬも天命の尽くる日は来む椿は咲きて
踏ん張るもこのあたりまで流れきて風の随(まにま)にゆく小さき蝶
そして悲しいけれど記すべき事実がある。娘の挽歌である。
温もりの伝はりてくる頭蓋骨 壺に収むるふたひらみひら
生垣をくぐり抜けたる白き花生きたかりけむ生きたかりしよ
愛別離苦、生老病死は世の定めではあるけれど、逆縁の愛別離苦と病の悲苦は筆舌に尽くしがたい。「ふたひらみひら」「白き花」と厳しく抑え込んだ表現に深い悲しみが宿っている。