青磁社通信第二十四号VOL.242012 年 6 月 発行
巻頭作品
青山・根津美術館
亡き人の世界へ差した傘ならね花びらの雨しづかにはらふ
たくさんの人と別れた春の暮れ影なき燕子花図にたどり着く
業平が消され八橋消されたり金地に影のない燕子花
日本の竹のみどりの雨を見てガンダーラ仏のあたまはだまる
完璧なうつくしさもて雨落つる現代日本瓦 自死やまぬ国
亡き人を語りて書きてそののちにもつと本当のことを思ひ出す
ばりつ(、、、)として空虚で仏に似るをとこ門番としてプラダ・カルティエ
エッセイ
二月の極み、三月の嘴(は し)
朝、空をまっしろに覆い尽くして雪がしずかに降っている。指でふれるとすぐにとけてしまうようなはかない雪粒ながら、屋根や車、枝先、ソーラーパネルなどに少しずつ積もってきている。うるう年の二月の最後の日。これがこの冬最後の雪になるのだろうか。雪はどんどん強くなり、空が真っ白、街全体もまっしろだ。世界がリセットされていくようである。
昼すぎに仕事を一段落させて、カメラを持って外にでかけた。雪はさらに降り積もり、あたり一面まあたらしい白で覆い尽くしている。自分の身体にアドレナリンが充ちてくるのがわかる。豪雪地帯で雪に苦しんでいる方には申し訳ないけれど、滅多に降らない雪が積もると無性に楽しいのだ。まだ雪は少し降っていて、傘をさしながら公園に向かう。まだ誰も踏んでいない雪原がそこにあった。足を踏み入れると、膝下まであるブーツがざっくり沈む。抜く。沈む。抜く。雪、雪だ。足の下がぜんぶ雪だ、と思う。足を踏み入れるたびに雪が、ナニカ? ナニカ? とかすかな声で質問を投げ掛けてくる気がする。
うれしくなって、あまり人が足を踏み入れない森の中まで入りこむ。雪はだんだんやんできていたが、さしている傘に、ときおりどどどん、と雪が当たる。樹が葉に積もった雪をときどきどさっと落としてくるのだ。ヤラレタ、と思う気持ちと、やった当たった、と思う嬉しい気持ちとが同時多発する。
柵の上に自然にできた雪の小山に枝や葉で手足目鼻をつけて擬人化をこころみる。ゆがんだ身体のゆがんだ顔のゆがんだ目鼻が、なんだか哀れで、愛らしい。昼の光に、積雪の縁はすでにとけかかり透明になってきている。明日には、わたしがつけた小枝も葉とともにゆっくりと土に落ち、水に戻ってしまうだろうか。ちょっとふきげんな人、やや困っている人、妖怪ベロ出し、樹上のお姉さま、などあだ名をつけ、その場に置き去りにする。
一夜の命と思われる雪人形をかすかに心に留めながら、鍋をつついた。昆布をしいた湯にゆっくりと、豆腐、こんにゃくの薄切り、春菊、水菜、生たら、豚薄切り肉を投入して煮ていく。鍋は、空気の乾燥対策にもなっていいねえ、と空気に溶けていく湯気を眺めながら、思う。四年ぶりのうるう年のうるう日に、久しぶりの大雪だったなあ、と、潤んでいくものを味わう。
次の日。やよいさんがつさんざんさんがつ。意味のない言葉をつぶやいてことほぎながら三月に入る。三月の最初に口にした食べ物は、うどんだった。夕べの鍋の出し汁に、冷凍うどんを投入したのだ。鍋の翌日の朝ご飯は、雑炊かうどんと約束されている。一人暮らしになってもその約束は守る。誰とどこでそんな約束を結んだ、ということもないのだが。
午前の家事を簡単に済ませたのち、書評を書くための本を持って外に出かける。そこここで水の流れる音がする。溶けた雪が、水となって流れているのだ。街全体が清浄な谷川化したようで嬉しい。一部残り、一部シャーベット、あるいは水となった雪の痕跡を踏みながら、昨日つくった雪人形に会いに森に入った。しかし、もう、果たして、どこにも誰一人いなかった。「妖怪ベロ出し」のベロに使ったりゅうの髭が、残雪の上にペタリと落ちていただけだった。もう不機嫌でも困ってもおらず、誰かを脅かしたりも、気取ったりも、しない。
無常観を感じながら、近くの、魚が得意な居酒屋店に入り、ランチの鯵の塩焼き定食を注文したあと、ふと隣の席のご老人が食べているあら煮大根が目に入り、あ、あれにすればよかった、と瞬時に思う。ほかほかと湯気が立つあら煮。ゆっくりと箸を動かすご老人のその身体から、美味い、という呟きが漂う。ますます後悔の念がつのった十五分後、自分が注文した鯵の塩焼き定食が届く。身をほぐすとき、ほんのり湯気がたち、鯵もきちんとあたたかい。でもあら煮だったらもっとあたたかだっただろう、と思ってしまって鯵に悪い、と思う。鯵は焼かれて大きな瞳が真白になっている。はっとする。食用の魚の目を、目として意識してしまうと、いけない。とたんにそれは「食べ物」から「生き物」に変化してしまう。ごめんよ、とまじめに、鯵に思う。こんなにふざけた生き物に、食べられることになってごめんよ、と思う。あら煮の未練を空気に溶かし、どこかの海で捕らえられたであろうこの一匹の鯵の運命を、我が身に受け入れることに専念した。
我が身に受け入れた鯵が、私の内臓の中でゆっくりと溶けていくとき、浅い春の日差しを受けて、昨日つもったばかりの白い雪もどんどん溶けて水になり、さらさらと流れていった。
旅路より奏でる人生譜
杉本こすみ歌集『歴日』

そのかみに流人運びし船旅のながきを思ふ佐渡への航路
應仁の乱の槍痕釈迦堂の太き柱に深ぶか残る
見はるかす弁慶果てし衣川岸辺に生ふる草木茂る
三百年の角屋を支ふる大黒柱一尺八寸の四方(よも)煤けぬ
ひび入りし新撰組の墓石をゆるがすばかり蝉なきしきる
繰り返し歌われる旅路の歌。単に物見遊山ではない。歌人の行動力と探求心、視線の位置に必ず意志があるのだ。歴史の表舞台ではなく隠れた裏部分に焦点があるようだ。應仁の乱を見ていた柱の傷跡、嘗ての島原を行き交う人々の有り様、ともすれば義経に傾倒しがちだが歌人は弁慶を偲ぶ。振り向く人の少ない流人の苦しみを思う。新撰組の運命を痛むかのような蝉時雨の響みに耳を欹てる。多分それは命の儚さ無慈悲に喪失する悔しさを知っているからだ。
春雨に濡れて届きしザラ紙の夫が戦死の公報忘れず
征きしまま遺骨なき夫ふと思ふ父知らぬ子の花嫁姿に
生(うま)るるも同じ月日の甥なりき癌にて閉づる五十五年を
嫁ぎ来て看取りし姑(はは)の五十回忌すぎたる今日も改名となふ
母逝きて二十年経し姉の葬りふる里われに更に遠のく
多くの家族を見送くってきた過ぎ来しに感情を押さえ淡々と歌うが、かえって胸に迫ってくるのだ。故に一人であることを無駄にはしないのだろう。それは残されたあらゆるものへの労りともなっている。
過ぎし日に孫の楽譜を詰めし棚有名無名の歌集のならぶ
雛かざる部屋にただよふ雛の香を家族すくなき我はこほしむ
弥生雛かざりて部屋の華やげり客のごとくにつつしみ対ふ
友は歌人の身の内で絶えず見守ってくれている。そういう暮らし方をしている。そして一期一会を大切に思う。
海地獄の池に茹でたるあつあつの玉子をくれたる案内人よ
行きゆけど途切れぬ花の下をゆく散りくる花びら友となしつつ
靴片方波にとられて戸惑へば次にくる波その靴寄せく
土色の月の彼方に地球出づ万物いだきて青きかがやき
波が奪う靴を波が再び寄せて現れる。生きることは二つ得ては一つ失うことなのだと。その繰り返しの中で旅路の中で得た哲学が人生の譜となって奏でられているのだ。
孫背負ひ母がうたひゐし子守歌「地獄極楽この世にござる」
純朴で清潔な抒情詩
新谷洋子歌集『詩人のハープ』

「塔」入会後を学びつづけた約十三年間の作品より自撰された五四七首を収める。
朝ごとにもぎたてを食むミニトマトサラダの器にこぼるるほどの
背番号貰いし日より末の子の挨拶の声大きくなりぬ
雑草のすがしき朝よ抜くほどに指の先より目覚めゆく身体
作歌初期の右の作品、素直に詠って、純朴で清潔な詩情がゆらぐ。
夫と子の後姿(うしろで)追いしかの夏は鳴き砂の音響いていたり
亡き姑の愚痴聞かされし遠き日よ形見の時計腕になじみぬ
朝靄に潤む赤き実ゆすら梅退職をせし夫と食みおり
日常生活のかすかな断片を大切に掬いあげ無心に示された右三首。哀感にじむ追憶をそっと表白した歌に実質がきらめいている。
床ずれの日毎に消ゆる義父の身を蒸しタオル当て「聖水」に拭く
白百合を義父の目線に届くよう鉢に植え替え軒下に置く
オリオンの冴ゆる舞鶴後にして昼には奈良に薬を買いぬ
義父の介護、癌に逝かしむ夫との日々をうたう歌に生の嘆声が溢れる。一首目の「聖水」二首目の「目線」の語のひびきが強い。三首目。舞鶴に住む作者が遠く奈良に薬を求める。その固有名詞がよく働き、苦労がしのばれる。
激痛に耐えいる夫の細き身を支えておれば震えの伝う
外泊許可貰いて夫は帰り来し病魔は家にもついて来るなり
以後、激変する作者の身辺の歌は紙幅上伝えきれない。だが、ご子息家族と力強く生きられる姿を左記の巻末詠は生きいきと写象している。
うかららにせがまれて弾くピアノ曲「詩人のハープ」に指の撥ねいつ
この空の高みに
安藤純代歌集『五番目の季節』

ひと駅ごと春の濃くなる気配して内房線はここより無人
カモメらは力を捨てて風にのる力など最初(はな)からなかつたやうに
この歌集の背景に広がる房総半島の海が、とても美しくて魅力的だ。よく晴れた穏やかな海。そこにさんさんと降り注ぐ陽の光も、きっと明るくあたたかいだろう。そのような海を背景にして歌われるのは、アスペルガー症候群という障碍をもった息子を悩みながらも見守り育ててゆく、母親の姿である。
どこまでが個性どこから障害と蛙聴く夜の思ひはてなし
おびえつつ一歩一歩と後ずさる子の嘘かなし吃音かなし
アスペルガー症候群という障碍は、その障碍があることに本人はもちろん、周囲も気づかないことが多いと聞く。それでも周囲の人々とコミュニケーションをとったり、学校のような場所で集団行動に加わったりすることが難しいため、本人も、そして生まれた時から本人の一番近くにいる母親も、理由がわからないまま、どうして「ふつうの」生活を送ることができないのかと悩んでしまうのだ。作者の場合もそうであったらしい。
ある時は理解及ばず一篇の詩のごとくみる自閉症の息子
しかし、悩みながらもひたむきに息子と向き合ってきた時間は、決して作者を裏切ることはなかった。かつて共に悩み苦しんでいたであろう息子を、美しい「一篇の詩のごとくみる」と作者は歌う。この作者だからこそ辿り着くことのできた、そして歌うことのできた境地であろう。
この空の高みにたれか数へをらむ七の七十倍 海どりの影
悩んでいた昔と今と、「海」は変わったのだろうか。おそらく、何も変わってはいないだろう。海はいつでも、豊かに、おおらかに、はるばると広がっていたのだ。そしてわが子を見守ってきた作者の心もまた、変わることはなかったのである。
吐き出す、闘う、そして歌う
大橋麻衣子歌集『JOKER』

へたり込む姿照らされ白壁にわが影はただぶさいくな瘤
剥落をし始めた皮膚にんげんであるを疎みに疎みこのざま
放たれた途端に不満はすがた変え口から零れる大量の蛆
歌集を読み進めるのが、とてもつらかった。それなのに最後まで読まずにはいられなかったのは、なぜなのだろう。この作者の歌う世界はどこまでもひりひりとした痛みや憎しみ、怒り、嫌悪といったネガティブな感情に満ちていて、不安定だ。それらが夫やわが子に対して、友人や知人に対して、そして何よりも自分自身に対して、手加減なく叩きつけられる。「赦し」がない。作者は幼少期からの深くて大きな傷をずっと心に抱えていて、その傷口からは今なお真っ赤な血が流れ続けているのである。あまりにも壮絶で、表面的で安っぽい共感や慰めの言葉など、すべて拒絶されてしまう。
色鉛筆三十六色キンキンに芯を尖らせ安堵しており
人込みを突破したくて急ぐ足足足足足どれがわたしの
作者にとって歌をつくることは、つらく悲しかった幼少期からの痛みや悔しさ、憎しみを全て吐き出して闘うことなのだろう。「キンキンに芯を尖らせ」ているのは、「色鉛筆」だけではない。「突破したくて」「どれがわたしの」かわからないほど「急ぐ」のは、闘っているからだ。全てを乗り越えて、自分を奮い立たせ、生きるために。そんな闘いの中から絞り出される作者の絶叫、あるいは嗚咽が一首一首の歌となった時、読者を惹きつけてやまない強い力をもつのである。
歌集の後半、おそらく作者自身も思いもよらなかったであろう出逢いが訪れる。闘い続けた作者の目の前に現れたその人と共に見つめる世界は、どのように変化していくのだろう。
落ちてゆく十字架うすぐもりの空を眺める裸眼にあれはひ…
かなしみが美しい
本嶋美代子歌集『木の長椅子』

「ではまたね」受話器を置けばサイダーの泡のごときに包まれてゆく
声高く電話している若者とすれ違う時よき香りせり
五ミリほどの蟷螂の子は鎌上げてもよよもよもよ草をはいゆく
あいさつをしているような雀二羽互いに首をこきこきとして
日常によく見かける風景だが比喩やオノマトペがとても楽しく効果的だ。サイダーの泡で爽やかさを表す。街角の青年から漂う香りとは若さなのだろう。生き物たちの愛らしい仕草も見えてくる。そして歳月の花園には絶えず咲かせる想夫恋が散りばめられる。
出で来たる未現像フィルム手に重し命ある日の君がいるはず
そういえば一人だったとつみれ汁の多さに気づく蓋開けた時
結露せる窓にへのへのもへじ描(か)く亡夫に冗談言いたくなって
君逝きて止まりしままの時が今動き出しおり細波のごと
降り出しし雨に亡夫のサンダルを屋内(やない)に入れて揃えおきたり
つみれ汁、フイルム、窓に描く文字、時の細波、サンダルなど、夫は歌人の息の緒と共に生きていて相聞のメッセージを猶も送り続けているのだ。それはまた母への思慕にも繋がっている。
ラズベリーソースの紅の鮮やかさ「ほら、お母さん」と天に向けたり
留守電に生きてわが名を呼ぶ母の声やわらかし幾度も聴く
思いの隙間を癒やしてくれるものがある。
たわむれにダンスの拍子とりおれば猫が尾をふる一、二、三、四
たわむれに猫の長き尾なでおればそのするするに心がゆるむ
「母さんが死んでしまった」膝の上の猫に語れば吾を見上ぐる
無辜なものに語るとき堪えていたものが一気に弛んだ。昇華された悲しみの美しさ、春の宵に余韻となった。何時までも。
花は自立している
秋元和子歌集『幾春秋』

短歌にはほど遠きと思ふ子のわが歌に厳しき批評をすなり
短歌(うた)作るひととき忘るる身の不調時をり涼しき風通る窓
短歌(うた)に残す旅の縁(えにし)のはしばしに子を思ふ心亡父(ちち)の哀しも
散歩すれば短歌(うた)ひとつ出来る喜びに疏水の水は夏を匂はす
短歌への情を込めた作品を引いてみた。ここにはごく自然に様々な家族の表情が読みとれる。どこかホームドラマを見ているような味わいだ。歌人の目から映し出される家族模様の機微が優しい漣を描く。
読んだのか読まぬのか知らずわが歌を夫は一度もほめしことなし
夫への想いには人生の悲喜交々が歌われる。
生まれたるばかりの吾子の手足の指を数へしと云ふ被爆者夫は
手をそへて歩む二人の春にして背に暖かき陽を溜めながら
癒されてゐる秋の日の寂けさに夫の淹れたる熱きコーヒー
ゴルフ道具総てを孫に譲りたる夫の一つの時代すぎ去る
デイに行く夫を見送る車椅子の背に手を振りて吐く息白し
だが歌人は自立している女性でもある。
風のままゆれて散りゆくコスモスはわが誕生の十月の花
花ばなと心豊かに生き度くてベランダの鉢に植うるフリージア
思ひ出はみんな仕合せ手を当てて胸の鼓動のひびき確かに
わたくしの七十代が詰まりゐる十年日記重たく閉づる
花ばなは多分歌人自身の姿なのだろう。過ぎこしを懐かしんではいてもしかし、歌人は常に前を向く。その一途さがどこまでも歌になって心地よく伝わってくる。
ちぎり絵を貼りたる団扇(うちは)に書き添へるわが歌一首すずしき風に
拾ひ来し数葉のもみぢで作りたる栞に添へるわが歌一首
混ぜくって、手渡されたもの
河野裕子
伊藤一彦
真中朋久歌集『シリーズ牧水賞の歌人たちvol.7 河野裕子』

河野裕子は、二〇〇二年、歌集『歩く』で若山牧水賞を受賞した。本書は、「シリーズ牧水賞の歌人たち」の四冊目にあたる。インタビュー、代表歌三百首、エッセイコレクション、河野裕子論、著書解題、詳細年譜など、歌人・河野裕子の仕事を一望できる充実した内容になっている。
本書にも再録されている牧水賞受賞時の講評では、四人の選者全員が「寂しさ」というキーワードを用いている。確かに、『歩く』には、「さびしさよこの世のほかの世を知らず夜の駅舎に雪を見てをり」のように直接「さびしさ」という語を用いた歌や、「死んだ日を何ゆゑかうも思ふのか灰の中なる釘のやうにも」「どのやうな別れをせしか爪立ちて鞍を置きゐる人と馬とは」など、死や別れを意識した作品が目立つ。『歩く』と『日付のある歌』が制作された頃は、一度目に乳癌が見つかった時期と重なっており、作者の心の揺らぎが、短歌にも滲み出てきていたのだろう。
二度目の闘病中に編集された本書もまた、「この世のほか」に思いを馳せるような「寂しさ」の気配が、そこはかとなく漂っている。
印象的だったのは、エッセイ「三冊だけの歌集」。『歩く』のあとがきには自身の病気についての記述があるが、高齢の母がそれを読んでショックを受けることがないよう、母に送る分の三冊だけ、その記述を削除したのだという。母への深い思いやりを感じてしみじみと胸に迫るエピソードだが、一方で、その三冊以外を手にした私たち読者は、短歌と一緒に彼女の人生も手渡されていたのだなあ、と改めて考えさせられた。短歌も人生も、ほとんど息をするような自然さで手渡してくるのが、河野裕子の流儀だったと思う。
ついしんみりしてしまったが、もちろん本書は「寂しい」ばかりの本ではない。
伊藤一彦によるロングインタビューでは、子供の頃のこと、親友のこと、家族のことなど、歌の背景が豊かに語られる。『母系』の「あをぞらがぞろぞろ身体に入り来てそら見ろ家中(いへぢゆう)あをぞらだらけ」について、「やっぱり青空ってすごく不安なものじゃないですか」「あまりにもこの世が明るすぎると怖いんですよ」「内面と外があまりにも違いすぎるとちぐはぐします」と自解しているのが印象深かった。
吉川宏志との対談では、作歌の秘密に迫るやりとりが交わされていて嬉しい。『日付のある歌』について語った「場面はやっぱり最大限利用して、やれることをやる。(中略)何もかも混ぜくったところでのおもしろさって、あるでしょ。それを切り捨てていったら、どこか痩せていくような気がするんやなあ」という発言に、河野裕子の本質があると思う。
豊かな精神
重田裕子歌集『木洩れ日の下』

七七三首を、収録する第二歌集。「ハハキギ」所属。
十八年間の作品が、Ⅰ部Ⅱ部の分冊で収められている。家族に恵まれて幸せに年齢を重ねてゆく日常生活の中での豊かな精神の織りなす作品群である。長い年月の時々の思いが細やかに表現されている。
地に低き花々はみな影曳かずありたるままに春の陽を享く
わらわらと崩るることなき花ならむ安けく苞のなかに衰ふ
嘱目詠であるが、花の命に人間を見ている。「あとがき」に〈身辺を題材とし、「実に入り虚に出る」というように詠むことを理想としています〉と記されている。生の感動を詩に昇華させる過程に思索がある。思索によって現実をろ過して作品を作ることを心がけているということだろうか。
無名ゆゑの豊けき生涯を読み終へて梅雨のひと日の心潤ふ
踊り子はしなやかならず後姿の背にゆるぎなき骨格みせて
作品の多くに読書や芸術鑑賞の跡を見る。歌に幅や深さのある由縁である。一首目は結句で自分にひきつけている。二首目の踊り子を描いたのはジャンセン。美しい踊りを支えている強靭な背骨を描いた画家のテーマを自分のものとして詠む。
海境をへだててさびし樺太に往きて戻らざりし人のいくたり
賤ヶ岳登るリフトのたゆたひてこのうつし身の重さはかなし
集中にある多くの旅の歌には、見聞に心が添っている。一首目は、北の旅で甦る記憶が哀切きわまりない。樺太が日本の領土であった時代を知る世代である。二首目は宙吊りの空間での存在のはかなさの認識。
最後に家族詠の佳作を一首。
林檎の色変りはじむるテーブルに時間ずれつつ家族ら集ふ
個性的な感受
石本照子歌集『初冬の光』

四一一首を収録する第二歌集。「塔」所属。
爪の伸びる程のようにて指の傷むぐりむぐり治りゆくらし
実感が大胆なオノマトペで表現されている。既成の短歌的美意識や表現とは異なる作品が多い。
骨抱くわれに疎ましき新緑の中にほととぎすいて又鳴く
洋服屋酒屋電器屋散髪屋夫を悼みてみな来給いつ
底見えぬ穴に向いてわれの呼ぶ夢を見ぬ兄は二十二歳で死んだ
挽歌に作者の特色が際立つ。一首目、新緑の中に鳴くほととぎすの声を「疎ましき」と読んで湿りを払っている。二首目、弔問客をその商売を並べて表現してユニークである。三首目は、夢に托した真情の吐露。上三句は下句を導きだすためのレトリックであろうか。亡くなった子供の魂を呼び返すために深井の底に向かって大人たちが叫ぶ痛切な映像を見たことがある。戦争で若く不条理な死を遂げた兄君への思いは普通の表現ではおさまらないのであろう。結句の口語表現が効いていて、したたかな表現者だと思う。
ソプラノの声がふわりと弦楽に乗りたりフォーレ「やさしき歌」
突堤の先まで並ぶ海猫が一羽ずつ去る近づく程に
個性的な感受の光る作品で、一首目は楽器の演奏で歌いだす瞬間を巧みに捉えている。二首目は虚実皮膜の間に成り立っていてリアリティがある。
ご主人亡き後八年目の上梓ということで、次のような佳作もある。
だんだんと命令口調になりてゆく健康気遣う子よりの電話
向うから来たのか私が呼んだのかはっきりと夫が見え来て覚めぬ
自在な歌集
小澤婦貴子歌集『紅き塩』

ヨルダンに涙壺とふものありて遺されし者の涙量ると
抑制された心情表現が小澤さんの身上かと思うが、この歌にも悲しみを必死に堪えて歌に昇華させていこうとする意志が明らかだ。また、ヨルダンをはじめ異国への心寄せ。結句の言い差しなど表現面で様々に工夫を凝らすのも、大きな特徴だろう。
重ね着をしてゐる春の霞かな 段丘の端(はな)の薄墨桜
地力なきビルのあはひにしらしらと病衣のごとく桜咲きゐる
春霞の濃淡を「重ね着」と言うとは面白い。反対に、「病衣」は文明批評として切れ味の鋭い比喩である。桜という王道の歌題にも独自の解釈が施されており、読むたびに一つ発見がある。
欧州の空を斬りゆく飛行機のあまたの傷の交差する空
昼月と浮雲いづれ軽からむ おぼろにうかぶ春の天秤
飛行機の航路を「あまたの傷」と見立てる。幻視の歌とも、利権争いの風刺とも取れ、深みがある。また、昼月と雲の重さを量る歌など、想像力を伸び伸びと働かせた歌も面白い。歌材を限定せず、アンテナを広く張り巡らせていて頼もしい。
夢、力と書き散らしゆく書初めの〈夢みる力〉となりてゆくまで
学校生活を活写した歌。力強い運筆の様を窺わせる「夢、力」の表記が巧い。修辞のフィルターを通して生徒と接するからか、どの表現にも節度があり、清々しい。また、次の、いい具合に力が抜けた歌には作者の飾らない姿が見え、好感が持てる。
洗濯機の絞り機回せばのし烏賊のやうにシヤツなど出でてきたりぬ
「のし烏賊」の軽妙な比喩につい笑ってしまった。詠い方もテーマも自在な歌集に仕上がっている。持ち前のバイタリティを生かして、これからも様々な試行を重ねていかれることを。
「思索的抒情」の追求
三田村正彦歌集『エンドロール』

京都の西陣織の家に生まれながらも公務員を続けている作者の、二十五年に亘る作歌活動を集大成した第一歌集である。あとがきによれば、作者は若き日に春日井建歌集『未成年』に魅了され、さらに前衛短歌に惑溺した中から「思索的抒情」の追求へと進んで来たようだ。
エンドロールから見始むるミステリー映画のやうな会議であつた
織人の粘り持たねば公僕になりし報いのふにやふにやの腕
月光町九百番地シースルーエレベーターに取り残されて
この歌集を貫いているのは、馴染めないまま身を置いている役所勤めの疎外感や自虐心と、父親の仕事を継がなかったことへの自責という負のスパイラルである。作者にとって、そこを突破していくための道が短歌であり、昇華していくための「思索的抒情」の追求であったのだろう。
山積みのペットボトルが一体の光に変はる たそがれが来て
集中には光とか輝きを詠んだ歌が随所に見られる。鬱屈した自己凝視の一方で、これらの自己救済と見える歌がバランスをとり、光のスパイラルへの転換を予感させる。
うす蒼き闇を夜灯の道なりに鬼をかかへて少女が走る
幻想絵画風の魅力を持った一首。自己凝視だけでなく、別の視界を開くことで歌集に広がりが出た。
夕されば鍵を取り出す素足なる少年 夢に父に会ふのだ
最終章に置かれた父親追悼の連作の一首。この一首によって負のスパイラルは断ち切れたのではないだろうか。
『エンドロール』は、疎外感や自虐、自責という負の感情の迸りを、如何にして詩に昇華していくかという、真摯な苦闘の軌跡が窺える歌集である。
清新さと人を恋うるこころ
田中濯歌集『地球光』

九〇年代は疾うに過ぎ去り、ゼロ年代さえ終わってしまった。そして田中濯第一歌集『地球光』を、大いに共感し、またある照れを持ちながら読み継いでいた。というのはこの歌集もまた、九〇年代という時代の不景気さをもろに受けた青春の翳を如実にまとった歌集だからである。
CDの音がきちきちとぶ夏に猫の忌日はとうに過ぎたり
ポケットの硬貨を鳴らすさみしいと一筆書きのようにいうのか
Ⅰの京都在住期の叙情と表現は、実に端正かつ正統派の青春詠。かつて所属した京大短歌会の先達の影響を指摘することは田中には不本意かもしれないが、筆者には無視できない。
自転車に踏みし団栗はじかれて時間の枠を超えてゆきたり
すっきりと財布の小銭消えしとき我が日曜日完結となる
あとがきにもあるが、二〇〇一年からは約五年間の空白期があり、Ⅱは復帰直後の作品。田中は「第Ⅰ部と第Ⅱ・Ⅲで歌風が異なっている」と書く。たしかにⅠでは特に相聞にまつわる抒情がしばしば事物を上回る印象があったのだが、Ⅱでは事物の描写が表現の主軸となり、そこに作者の抒情が思索や煩悶をともなって表れる歌に移行してくる。言葉と抒情の方程式が見えてしまう歌が散見されるのは残念だが、Ⅱ以降は歌が呼吸しているというか、表現と作者の内実が有機的にリンクし始めている。〈水銀のはつか染みいる抗体は春を越えたり新しきまま〉も、自然科学の事象の美しさに立ち止まる作者が印象的だ。
ポスドクは「派遣」に過ぎずさびしかる肉欲などもやはり備えて
プライドがわれらを締めてゆくあいだポテトサラダは胡椒を浴びて
石塀の続く静かな道なれば「不動道」なる名をもて続く
その後、田中は盛岡の大学に職を得て転居、Ⅲはそこに材を得た歌が中心となる。読み進むにつれて歌の表現は手堅さを増すが、随所に清新さへの希求が見られ、一冊がすぐれた青春歌集たり得ている。むしろ歌集総体に流れる諧調は、相聞というよりは、人を恋うる心そのものと思える。個人的に好きな歌も多く、〈ペルシアは旧国名と知りてより曇天に青映える春寒〉などはやや作り過ぎの感は否めないが、気に入っている。
だがこの歌集刊行後しばらくして、東日本大震災が起きた。盛岡で被災した彼が、今後どのような形で自らの感情を歌にするか。第一歌集に満ちた美しさと清新さへの希求はどのように変容し、第二歌集へと収斂してゆくのか。注視している。
家族の食卓
池田はるみ歌集『南無 晩ごはん』

『南無 晩ごはん』という集名のとおり本書には食べ物が多く登場する。詠われるのはどれも伝統的な日本の食べ物である。
のこぎりに落とされし尾を祭りをり降誕祭のまぐろの光
牛丼にたつぷりそへる紅しやうが空火照(そらほで)りとふ言葉おもほゆ
降誕祭に祭られるのは輝くまぐろの尻尾、クリスマスの光景としてはまことに異形の歌といえよう。牛丼に添えるあざやかな紅しょうがを「空火照(そらほで)り」という井原西鶴の『好色一代男』の夕焼けの世界に広げてゆく。どちらも印象的な歌である。
麦ごはんを食べた記憶はいちどきり小さいわれが人にかこまれ
雨の夜にうからの赤子を交へつつもの食ふことを幸ひといふ
幼年の記憶のなかの大阪の家族の風景。歳月が過ぎ、息子に赤子が生まれ食卓の中心になった。幼児を囲む食卓は「幸ひ」であり、守るべき「砦」なのである。
美しきみどりごあかね昼を来て風邪のなごりのくしやみをしたり
三歳のあね這ひ這ひに追ひてゆくしばし考へまた追ひてゆく
孫の頌歌はためらいがなく衒いがない。「みどりごあかね」という言葉はこびの美しい上の句から、赤子のかわいいくしゃみに繋げてゆく。二番目の女児は「あおい」という。這い這いをしながら姉を追いかけてゆく姿がいきいきと描かれている。
この世ふと分からなくなる姑さまや白いごはんはこころを開く
新しい命が誕生したこの時期はまた姑が病み、記憶を失い、逝去する、たいへんな数年でもあったようだ。姑の歌は多いが、重苦しくなくときにユーモアさえ感じさせる。姑に寄り添いながら、対象化して詠われているからだろう。
四世代みなが揃ひて食事せりそののちあらず一度きりなり
夕べには日ごと日ごとに言ひにけむ「ご飯はすんだ?」南無晩御飯
姑と夫と作者、そして息子夫婦と孫の四世代が揃った家族の食卓はこよなく懐かしい時間として詠われる。生の根源である食事を家族と囲むことができる有り難さが、東日本大震災以後の現在、いっそう身に沁みて思われる。「南無」という言葉が、この世の家族と、亡き家族たちがまじりあって食卓を囲んでいる風景を浮かびあがらせているようだ。
独りでいるときの作者の表情、存在の根源にあるさびしさを感じさせる巻末の一首を抽いておきたい。
いつしかに霰となりて横降りの清砂大橋わたりゆくかな
秋に咲く桜を見上げて
岡本幸緒歌集『十月桜』

半地下にピアノ教室ある路地に高き音のみこぼれていたり
ふるさとはいつもだれかがわれのため二つの茶碗で茶を冷ます場所
はらわんとあなたがわれの髪に手を伸ばす合間も雪降り続く
きっと優しい人なのだ、と思う。いつも歩く路地の風景や、そこに聞こえてくるピアノの音。移り変わってゆく季節とその空気。「二つの茶碗で茶を冷ま」してくれる両親たちの住むふるさと。そして、作者の傍らに寄り添う、「あなた」。作者の繊細なまなざしによってとらえられた、ささやかな日常。歌われた一首一首はどれも、やわらかくあたたかい。
造影剤右ひじあたりにとどまって重心ずれるような感覚
日本語訳核磁気共鳴映像法 春と秋にはこの筒に入る
作者はしかし、あまり症例のない難しい病気を抱えているらしい。「核磁気共鳴映像法」とは、医療用MRIのことである。今なお定期的に「造影剤」を飲んで検査を受けているのだ。心身ともに大変な負担であろう。しかし作者はその痛みもまた静かに見つめ、時に涙をこぼしながらも歌として昇華させようとする。「重心ずれるような感覚」は、この作者だからこそ表現することのできる身体感覚だ。歌集の中で具体的な病名が明かされることもなく、大仰に辛さが訴えられることもないが、だからこそこれらの歌も、読者の心に確かに残るのである。
黙契を結ぶのだろうこの秋も十月桜の前に立つとき
作者のあとがきによると、歌集のタイトルとなっている「十月桜」は、春と秋の二度咲く八重の桜だという。この「十月桜」が、歌集の折々にやわらかく花をひらく。作者の抱える病も流した涙も、全てをそっと包み込むようだ。八重の桜は、今年もまた咲くのだろう。作者は八重の桜を見上げながら、また静かに言葉を紡いでいくのである。
普段着の言葉
青木朋子歌集『大空の亀』
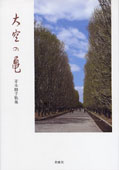
蝉密度高きこの夏ベランダのインコはまねぶ熊蝉の声
独り居の我を見つめて家猫は逆三角形のあくびをしたり
表現が難解ではなく、歌を読むのに特別な知識を必要としない。言わば普段着の言葉が使われているのは青木さんが教師だったからだろう。日常と地続きの地点に歌を置くことで敷居を低くして面白さを伝えようと、敢えて易しい表現を用いるのだ。だが、歌は決して単純ではない。見よ、「蝉密度」の似非物理っぽい把握の妙。欠伸する猫の口の形を逆三角形と看破するユーモア。的確で洒落っ気のある表現は相当の力量を必要とする。
図書室に逃るるやうに来る子ゐて本はやはらかな楯と思へり
「この夕焼け詩にしますね」と女生徒の言ひて二日後届く「夕焼け」
本を心の糧にして学校生活に耐える生徒には思春期の青木さん自身が反映されているのだろう。穏やかな表現の中にヒリつくような生きづらさを感じる。「夕焼け」の詩の背景にある生徒との温かな心の交流。生徒の内面に深く踏み込むことはせず、立ち直る力がそれぞれにあることを信頼して見守る。誠実な対応は、「再生「十五歳」」に詠まれた恩師に影響を受けたものか。
贈られしノートに「はる」を写したり そらをこえかみとはなしをしたといふ詩を
「再生「十五歳」」は十五歳の自分に成り変わり、母の死から立ち直るまでを詠んだ連作だ。言語化することは傷を癒すことでもあり、生まれ変わる為に必要なイニシエーションだったのだ。
カッターの刃先替へたる春の午後鋭く裂きたきものなどなきに
相反する感情は新たな世界に踏み出したいという願望の表れだろう。第一歌集の世界を発展させつつ壊しつつ詠んでほしい。
柔らかな感性
上杉和子歌集『絵地図』

自然体でありながら懐かしいような手触りのある歌集である。
時折は触(さや)りてもみる亡き父が煙草であけしカーテンの穴
炎天の駐車場の隅ざつくりと置かれた鎖が這ひだしさうで
煙草の焦げ痕はささやかな、それ故幸せに満ちていた日々の象徴だ。また、「さつくり」の音の生々しさは、這いだしそうな鎖という比喩に説得力を与える。どちらも一見、平凡な光景のようだが一首の背後には煙草好きの父親、無造作に鎖を置き去りにした何者かの姿がそれぞれ垣間見え、意外な奥行きを示す。歌に手触りがあるのは時間の厚みを抱えているからだろう。
焼け爛れし前輪駆動車の眼窩深し半年を経てなほ空に向く
非日常を題材にした時もその姿勢は変わらない。提出歌は阪神淡路大震災を詠んだもの。即時的に反応することは誰しも可能だが、時間をかけて変化を見つめることは難しい。壊れてしまったライトを「眼窩深し」と喩えたところに批評性がある。
蛇の尾はこんなに細く尖りゐると抜け殻なればまじまじと見る
とりどりの鬚髭(しゆし)つけ鎧並びゐて隣のひげと較べられをり
また、上杉さんは優れた観察力の持ち主でもある。蛇の抜け殻の先端が細いこと、鎧の鬚髭(しゅし)が様々なことなど物事の細部を丁寧に見つめる。実直な言葉運びに発見の喜びが溢れている。
ほんたうの名まへは知らず雨ふふむ山道酸つぱいててまるの朱実(あけみ)
綿飴の湧き出づる機械あてがはれ今宵うつとりわれは綿雲屋
一方、視線を緩めて曖昧な感覚を曖昧なままに留めた歌にも惹かれる。素直な表現は風通しが良く、心地いい。何気ない光景をノスタルジックに詠いあげられるのは感性が柔らかい証拠だ。この先も、心がほぐれるような歌を作り続けてもらいたい。
表現の角度と五感
尾崎知子歌集『笹鳴り』

『笹鳴り』という歌集名は
かさかさと笹の葉の鳴る山の道葉と葉の間(あひ)より冬になりゆく
よりつけられたと思うがこの笹の葉ずれのおとがする山道こそ作者の現風景であり歌人としての情感の根源をなすものであり、笹の音は常に柔らかに作者の胸に響いているものであり、忘れ得ぬものであることが感じられる。
一つ一つの事象への焦点の当て方がこまやかであり、とらえ方もユニークで、時には不気味なぐらい存在が明確に描き出されている。
まよふ日にのぞいてみたる万華鏡ばらばら足跡落ちてきたれり
子どもらが花びら貼りて絵を作る〈踊るサテュロス〉見に来し上野に
蛇口より小さき魚出て来ぬか、のぞいてみたら涙がぽとん
ぬばたまのをんなの髪は花のごとわつと広がるプールの水面に
自身の病、他人の病を客観的であるが優しく表現し生と死を凝視している。
電動の介護ベッドを傾けてまどろむ老女 過去は溶けゆく
車椅子に試乗する時われもまた低き視線に世界を見てゐる
氷水に触るるがごとき冷たさを指に残してをみなは逝けり
外来の待合室はほの暗く床に吸ひ込まれつつ眠れり
わが母の嫁入り箪笥開けるたびハモニカのファの音のするなり
物を見聞きする角度が非常に自在であり、触感、音感の濃やかさに感動させられてしまいました。
原風景へ
本田一弘歌集『眉月集』

どこからが今でどこから過去になるどうでもいいと綿雲のいふ
この一首が宣言であるかのように、現在を超えて過去の風土的な世界にまで作者の意識が飛翔してゆく感のある集である。
この春の一年生に早苗とふ清しき名もつ少女がふたり
一首だけを読むと平凡だが、直前の歌の「種を蒔くひと」、その後の歌の「松の嫩芽の伸びてゆく」少女子(をとめご)という流れの中で見ると、磐梯山の自然に寄り添うように、大地の息吹そのものとして育っている二人の少女の存在が浮かび上がる。
をとめらのけだるきこゑのひびきあふ とをてくう、とをるもう、とをるもう
この一首の下句は、萩原朔太郎の詩「鶏」からの引用である。
しののめきたるまへ
家家の戸の外で鳴いてゐるのは鶏です
声をばながくふるはして
さむしい田舎の自然からよびあげる母の声です
とをてくう、とをるもう、とをるもう
そうするとこの「をとめら」も人ではない可能性もあるが、一方で若い人の、どうにもならない倦怠の情を鶏声の擬態語で表しているのだとも言え、それはたぶんどちらでもあり得るのだろう。
あしびきの山鳥の尾の戦後とふ長長し尾をひきずるわれら
言うまでもなく百人一首の人麿歌の本歌取りだが、ポスト戦後世代の歌にしては珍しい感慨がある。「戦後」をひきずる主体を「われら」とやや漠然とさせているが、「あしびき」と「ひきずる」が響き合い、何ともいえない遣り切れなさが出ている。本当は「ひきずる」ことを押し付けられている吾らという裏側の声が聞こえる、というのは筆者の恣意的な読みか。
ケータイの画面突然赤いろに変はりて届け召集令状
最近出した拙集の一首に「@(アットマーク)まなこに見ゆる真夜中にふと来(く)や〈召集令状メール〉」というのがあるのだが、こちらはもっと緊迫感のあるイメージでもって歌われている。「赤紙」の伝統を踏まえた真っ赤な画面の令状メールという諧謔が効いている。
一弘よ引つがげねえで餅食へ(もぢけえ)と祖母に叱られわがゐたりけり
祖母の存在がこれほどに大きな若手の歌も稀有だろう。それもやはり風土的な重みの象徴としての「祖母」だからだが、そうした「風土」への回帰、あるいは「土俗」への傾斜がこれからの短歌において重要なファクターとなって来る可能性がある。
東日本大震災前に出た歌集だが、失われた原風景への思いは今後この作家においてさらに深くなることが想像される。
きさらぎの雪に甘噛みされながら吾妻山(あづま)と吾はねむらむとす
生命への感覚
武田久雄歌集『寒の水』

琵琶湖の湖北に住み八十路に入った作者の第二歌集。胸の病を負いながらの日々の暮らし、湖北の風土、東京や沖縄など各地への旅、父母への想い等、平成十一年から二十一年に至る間の様々に心を震わせた生命の軌跡が綴られている。
川越えて鼬はふかき雪のなか潜ると見えしに頸もたげゐぬ
小谷連峰のいづれの処より迷へるや猿が一匹野を駆けてゆく
街道の茶店のうら側鉄格子猪二三度われに尾を振る
この歌集で先ず印象深いのは、自然の中での動物たちを詠んだ多くの作品である。生命との出逢いに心惹かれている作者がいる。描写が的確で、情景が鮮やかに浮かぶとともに鼬や猿、猪そのほか様々な生き物たちの表情すら見えてくるようである。生き物の動きを描写する眼の確かさは、長年の作歌への研鑽によるものであろう。
突然にわれを襲ひし胸痛も過去とならぬやこのニトロ故
あと十年われは生きたし湖(うみ)に浮く船打つ波の音限りなく
生き物との出逢いが鮮明に伝わって来るのは、胸部動脈瘤を抱えた作者の、生命の希求の想い故であろう。出逢った動物たちの姿にも、躍動感より一抹の寂しさが窺える。
乙女らの自決せしとふこの壕のうす暗くして風なまぬるし
神職の家系にあらぬも守りゐる鎮守の森に雪ふりにけり
雨が雪に変る寒の日水をとる父の仕草をいつしか真似て
病は八十路での治療により事なきを得たそうである。生命を知る者は他の生命を想うことも出来る。そして杜を守り続け、亡き父親を想い歌集の題とする。そのような作者に天は共振したのであろう。
しっかりした写生を基調として生命を見つめるこの歌集には、心の時間が静かに流れている。
涼やかな句の立ち姿
藤田良二郎歌集『夏椿』

『夏椿』には、その句集名が示しているように清冽で揺るぎのない句が横溢している。内容と言い立ち姿と言い、文句の付けようのないほどの水準を誇る句が、おのおののページを彩る。
打ち水の手をやすめずに受け答へ
「やすめて」ではなく「やすめずに」と言ったところに巧さがある。玄関先に会話している二人の親しい関係性が、この一語によって表されている。
海の家畳まれてゆく渚かな
ひと夏かぎりの海の家が、虚しくも解体されていく。描写するのではなく、下五で「渚かな」と景を大きく捉えたことで無常観が引き立った。
菊剪るや相つれだちて鳥のゆく
つがいの鳥が飛び立っていった空には、秋のまぶしい日差しが溢れているだろう。「菊剪るや」の硬い音調とほのかな惨さが、明るい景のアクセントになっている。
着ぶくれてここは雪国風の町
「ここは雪国風の町」はという歌謡風のフレーズを「着ぶくれ」が程よく茶化している。
とんどの火飽かず眺めてゐる子かな
火を眺めている子は、どんなことを思っているのだろうか。大人にとってはまぎれもない「とんど」であっても、子供には全く別のものに見えているかもしれない。大人には推し量れない子の心中は、怪しくも魅力的だ。
産声やどの窓からも春の雪
春の雪が祝福して生まれてきたかのような赤子は、その肌も雪のように白く柔らかいに違いない。
郭公や野良着を山に向けて干す
生活の場である「山」への畏敬の念を、野良着の干しざまを通して即物的に言いとめている。
海に月映りしころを踊るかな
「海に月映りしころ」とは、海が凪ぎわたるころを言うのだろう。美的に演出された盆踊りの景が読者を酔わせる。
草の穂につもりし雪のやみにけり
吹けば飛ぶような、かすかな薄い雪に違いない。「草の穂」などという極小の舞台においても、雪が降り始め、降り止むというドラマが展開しているのだ。
このように、端正で俳句らしい作品が並ぶ中にも、不思議な風合いを持った句が、ときおり潜んでいるところが興味深い。
雪が降る終着駅であるために
「~であるために」と理屈のような措辞を取りながら、その実全く理屈が通っていないところに奇妙な面白さが発生している。雪が降ってこその「終着駅」、それは荘厳された死の象徴とも読めるだろう。
人生の厚み
古川利子歌集『金色となる』

四六一首を収録する第二歌集。「塔」所属。
小春日の日向のような晩年の時間を大切に丁寧に生きて詠まれた作品は過不足のない惜辞によって端正な歌の姿をなしている。自然の景や人事や心の動きを巧みに的確に表現する描写力は長年の研鑽の成果であろう。
雨の日の薄鼠の空静まりて黄のあざやかにツワブキ濡るる
父母ありて柿ゆすらうめ柚子すもも庭に穏やかな時流れいき
川の面をすべると見ていし水鳥の小さき足のせわしく動く
草花との親和の歌が多くある。一首目は背景に薄鼠色の空を配してツワブキの黄の花に光を当てた絵画的な巧みな描写である。歌集にはこのような歌が散見する。二首目は昭和の懐かしい景色を背景にした回想詠。別の歌で若く結核を病まれたことを知るが、歌集の歌は、生を肯定的に捉えて明るく、両親の愛情に恵まれて育った人の人柄の暖かさがにじむ。三首目は、巧みな詠物歌というだけではなく、水鳥の生態の描写が、生物が生きるということの本質にまで及んでいる。観察と思惟によって成った佳作である。
人道支援の派遣といえど隊列を組む行進の軍靴のひびき
言挙げの歌ではない。人道支援といえど武装して隊列を組んで国を出て行くものへのかすかな嫌悪感や、歴史を知る者として感じる危うさがある。平和で穏やかな生活者としての歌が多いなかに、さりげなくこのような歌が収録されていることで、作者の人生の厚みを感じさせる。これは歌集の厚みとも言える。
午後の陽のわが書見台に差し入りて読みゆく頁に小さき虹おく
姿勢を正して読書する作者の姿が彷彿する。このような学びの姿勢があっての作歌である。
家族への愛に溢れて
天野栄子歌集『白鳳台』

作品の
吾を待てる母を思いて花も見で白鳳台の坂登りゆく
より命名されたと思われるが、奈良県香芝市に実在する実家周辺への郷愁と父母への敬愛が深く感じられる。というのも集の始めに父と母を思い遣る作品を多く掲載したことにある。しかし敢えてここでは父母以外の作品の中から私のこころにきらめいて来たものを抄出してみた。
香にたてるメロンの果肉包みたる迷路のような皮を切りたる
七月の熱き遺骨を拾うなり明治男の気骨も拾う
大空にでこぼこの道あるらしくコップのジュース揺れにゆれおり
きらめける春の女神の豹変に帰路は嵐を突きぬけ走る
そも君は吾の責任と言うなれど狗尾草の風のままなる
全体的には父母を始めとするファミリーないしはファミリーを思いやる生活環境の感慨を愛をもって詠われ、表現は伝統的な静けさに満ちてはいるが古めかしいものではない。
限りなく脳は零に近づきて襤褸のごとくベッドに落つる
せまり来るカード社会に溺れゆく暗証番号ついにうかばず
海の色映せるままに汚れなき水晶体の鰯求むる
中空に風の生れたる気配して夢のかけらの肩に下りくる
ようやくに留袖の帯とき放ち京都の風に抱かれている
これらの愛に溢れた優しい詩情はその底辺に父母や家族を思い日々を大切に生きた者への天の褒賞として完成されたと思われるが、これからはここに抄出した家族を放れた詩情の世界へ目を向けられた素晴らしい作品を生み出されることを祈る。
実存と抒情
岩野伸子歌集『鉄とゆふがほ』

河野裕子氏の序文の中に/自分に表現形や資質が似ており自分自身のこころの底をのぞいているような錯覚に陥った/という部分があった。しかも著者の作品には胸のうちに厳然とした理論、思想があって詩へと難無く展開、融合してゆく。「鉄」は強い個の主張であり、「ゆふがほ」は反面の抒情であろうが、直喩的、直情的に読者の胸に迫ってくるような詠風でもある。
たちこめし霧かすかにも動きゆく〈時〉の刹那の中を歩みぬ
手から手へ螢を移すくらやみに顔なき顔を寄せ合ひてをり
しろたへの月光したたる夜深し死者になるまで試されて生く
羊水の世界より来てさくら咲く下界の空気を赤子は吸へり
辻褄は死ぬまで合ふことないだらう宙天を指す稲のまみどり
氏の作品には言葉のリフレインが多々見られる。短歌は短い詩型なので一般的には表現の無駄といわれるが、言葉を繰り返してリズムを作り意味以上のことを身をもって伝えるという離れ技に功を収たものも多い。例えばその極一部を抄すると
事務室に音なき時計掛かりゐて音なきものに縛られてゐつ
母はどこ母は何処かと石ころの道の石ころ見つつし帰る
など。また鴉に托してささやかな自己主張も面白い。
ニンゲンノコドモハウムナと鳴きしのち鴉は庭のさくらんぼ食ふ
死んでゐるあなたも生きてゐるわれも架空の人間だとカラスがいひぬ
実存を主張しながら実存への深い懐疑をもって生きている人間の寂しさが、抒情へと融合して「個」が浮き出されている。
膨らむ湖
三田村章子歌集『比叡山麓三丁目』

雪の比叡にただよふ雲を朱に染めて入りゆく夕陽は湖(うみ)はも照らす
伊吹山をくまなく映す三島池淡青の水は氷(ひ)を溶かしそむ
池岸に薄氷(うすらひ)動くを見てゐしが耐へ切れなくて沈みゆくあり
本書は第一歌集『奥能登・冬のあぢさゐ』後十一年余を経た作者の第二歌集である。
比叡山南麓丘陵地に四十年近く住まれ、歴史的風土ゆたかな土地に朝夕、こころを澄まし詠われる。一首目、しみとおるような写象が印象鮮明。ゆっくり(、、、、)と言葉を抒べて「湖(うみ)も照らす」と声調大きなゆらぎ(、、、)が崇高である。二首目三首目それぞれ現実の秩序をみつめ、匂うような静かに澄んだ境地をかもしだす。
張替へし障子はしんと匂ふごと雪かげろふを映して蒼し
かの世にて母は父に会ひ得しや紅枝垂れ梅ひとつほころぶ
夕空を押しあげて咲く泰山木昨日の雨の疵あらはなり
さくらさくら見渡すかぎり咲く桜父よ見に来よ母よ見に来よ
愛してやまぬ父母や親族の病や死をみつめ大自然のすがたを身にひきつけて詠み、胸中の鬱塊を吐きだすような歌が多い。
平成十八年九月に転倒後、腰の筋肉を裂傷する大怪我に長く苦しむ作品が痛々しい。
ひたすらにリハビリ励みし夏すぎて杖に歩める一歩また一歩
本当に痛いのはどこかおんおんと訳の判らぬ痛さに泣けり
病み永くからく耐へ来し三年余見えがたきもの見え始めたり
われ病みて祝ふことなき誕生日インターネットで電子辞書購ふ
生誕の日に辞書を買い祝われる歌にホッとし、左の歌の無限のゆたかさをまぶしむ私である。
六月の光を曳きて降る雨をうけとめ湖は膨らみそめる
流麗と重厚と
橋田政子歌集『空わたる水』

水浅葱の空ひろがれば登りゆく道かぎりなきあこがれに満つ
草かげに蝦夷紫陽花の青淡く原野にともる魂のいろ
群落の桷(ずみ)にまつわる朝霧のしずく真紅の実よりしたたる
『空わたる水』は好日入社後二十年間の作品を収める著者の第一歌集という。右に抜く三首。たくみに詠うがきれいごとの叙景歌ではない。流麗なリズムのなかに、本質を捉えようとする厳しい写実の眼が働いている。
まなかなる岩こえんとし渦をなす流れの疾し利根川上流
雲うつし風をうつせる四万十の流れのまなか橋を渡れり
一閃ののちをみるみる昇りくるしたたるばかり山の朝日子
山登りをよくされる著者の歌集には利根川や四万十川、御岳などの高峰にて素材をキャッチされ、大自然と一体となって心を澄まし、その特徴を鋭い感性で捉え、見事です。
「『嬰女』志保」の章の痛切な挽歌も収められ、父上母上、親しい友の死をみまもる歌も折々の様子、行為を簡潔にとらえて抑制が光る。
雨降ればぬれつつ歩み風吹けば吹かれて歩むわが遍路みち
蛇、蜻蛉、蝶、蝉、鼬道端の死にも出会いぬ真夏の遍路
ふりむけば泣きそうになる結願のお堂の上の岩山仰ぐ
栃の木の樹齢百年ざわめきは木下に厚く積む落ち葉から
「遍路」の章一連より。実際をよく見つめ独自で捉えた重厚な作品群が本集を深める。
左記はタイトルにされた佳品。「対象を見るように聴き、聴くように見て捉えよ。」と言われた大詩人の言葉が思い出され到達された境地の高さを思う。
空わたる水というべしせせらぎて流れる音の梢を伝う
抒情味のある内観
藤田とし子歌集『寒あやめ』

八十歳半ばを過ぎた作者が、生きてきた証として詠み溜めてきた歌を三百七十頁を越える大冊に纏めた歌集である。といっても、若い頃からコツコツと、ということではなく、五十代の時に病を負う中で、後々ベッド生活になっても出来ることをということで作歌を始められたそうだ。
忘れたき事の一つのふくれゆき花梨の蕾の朱(あけ)暮れのこる
追憶となりゆく事を拒むとき一際白き娑羅の花ばな
高だかとメタセコイアの円錐の突きあぐるもの吾が裡に欲し
心の奥を見つめる時、浮かび上がってくる想いの内容を説明するのでなく叙景に托して詠うことにより、心象が立ち上がってくる。その際、蕾の朱、花の白、高き円錐の樹というように、色や形を描くことにより、一首の印象が鮮やかに刻まれていく。
流れゆく一ひらの雲月に照るを吾が残生の祈望と思ふ
一般的に月を詠う歌は多いが、作者は月に照る雲に焦点を当てて見せた。工夫した作り方によって、夜空を輝きながら流れゆく雲のようでありたい、という心の詩となった。
夫と喰む茱萸への憶ひそれぞれの童に還る深き紅(くれなゐ)
亡くなられた夫君との日々を詠った連作は、過去と現在の時間が同時に流れているという表現が印象的である。掲出歌では〈それぞれの童に還る〉という表現に、夫と共に過ごす今の時間と個々の幼い日の時間がオーバーラップして、味わい深い。
二つ三つ病む身の歌詠み魂の炎は燃えよ残んの茜
巻末歌は、病みながらも歌への情熱を滾らせている作者の想いを未来へ送り出しており、歌集の終わりを締め括るのに相応しい。
『寒あやめ』は、現代ではなかなか見られない言葉や異体字を駆使しつつ、抒情味のある表現に富んだ内観の歌集である。

