青磁社通信第十七号VOL.172007 年 9 月 発行
巻頭作品
春の遊び
うらうらと山咲きのぼる桜見ゆ大堰川の辺を歩みてくれば
竹林の人歩み向うに桜透くさくらはしだれ濃き薄きあり
幼な松の勢(きお)う芽立ちの四月空明る曇りは鈍(にぶ)に輝く
桜まだ揃わぬ峡を舟下る水棹(みさお)の雫天をはしりて
尾伝いに桜咲きのぼり舟はゆくふたたび三度渦にきしみて
豊かなる水に揉まるる十余粁水棹ひらめくは岩突き放す
屈強の男揃えて岩衝きて舟は下れり谷尽くるまで
エッセイ
青磁のゆかり
私にとって旅の仕事が多くなったのは中年以後のことなのだが、「古典の旅」とか「染織紀行」とか、古典文学全集の月報で現地取材のエッセイを書くためなど、気がつくといつも列車の中、という時期があった。旅先ではあまりものを買わない方だが、いつの頃からか、その地方らしさのある「やきもの」を、一つ、二つ、と買い溜めてたのしむようになった。
青磁の器がはじめてそのコレクションに入ったのは、もう二十年も前になろうか。その日金沢にいた私は、犀川沿いの画廊を覗きにいったのだが、丁度大樋焼の展示会が開かれていた。私は現在の大樋焼を余り好まないので、奥の方をぶらぶらしていると、ガラス棚に押しこめられている小さな花瓶が眼にとまった。耳付青磁の、繊細な曲線が美しく、心が動いてそれを買うことになった。画廊の女主人によれば、まだ名の出ていない若い作家のものだとのこと。作品を包んでもらっている間に他の棚を覗くと、つめこまれたごちゃまぜの陶磁器の中に、ゆったりとした清楚な青磁花瓶があって、これがまた、何やら「おいでおいで」と私に語りかけてくる。秋の枯草めいた文様が浅く刻まれて、その自然な筆致がよかった。聞けば、いま私の買ったのと同じ作家の作だという。
旅先だし、重たそうでもあり、私は諦めてそのまま帰京した。が、日が経つにつれてどうしてもその花瓶が気になって仕方がない。一週間ほどしてから、金沢の友人に頼んで、とうとうこの花瓶を手に入れた。
その経緯を「陶芸の美」という雑誌に書いて、写真が載ったのをきっかけに、私はその作家、小松在住の堂前忠正という陶芸家と知り合った。まだ若く、純朴で、くりくりと眼が澄んでいて、私はこの青年を「どんぐりちゃん」とひそかに呼んでいた。或る時、「なぜ、青磁ばかり焼くの?」と訊くと、こんな答えが返ってきた。
「山が好きで、蔵王の山の湖、あの“お釜”をはじめて見て以来、何とかあの色を出せないかと思って」
不思議な縁だった。私には混声合唱組曲「蔵王」(佐藤眞作曲)という作品があるのだが、彼は高校時代にそれを唱って以来、蔵王に憧れたのだそうである。本来音楽を専攻したかったのに、金沢という土地柄には、音楽家は不良と思う空気があったらしく、陶芸なら許す、といわれて陶芸の道に進んだのだという。しかし、金沢では九谷焼が本流なので、青磁はほとんど独自の工夫で焼いているのだともいった。
以前私は、『源氏物語』の中ではじめて「秘色(ひそく)」とは青磁であり、宮家の食器として使われていたことを知ったのだが、蔵王山上湖の通 称“お釜”の、あの神秘極まりない色は、まさしく「秘色」というにふさわしい。ある早春、凍ったお釜を見たが、それさえ深い青磁色を保っていた。その“色”を追求している青年のまなざしは、今どきめずらしいほど、純に澄んでいた。
ところで、ここに青磁の話を書いたのは、じつをいうと青磁社の社名からの連想だったのだが、この「青磁社」の名自体にも、私にとっては懐しい思い出がある。
たしか昭和十九年の末ごろだった。私ははじめて佐藤佐太郎の歌集を手に入れた。文庫型の小冊子で、白地に臙脂色で「しろたへ」と印刷された清楚な表紙。その発行元が「青磁社」だったのである。戦時中といってもすでに末期、物資も極端に不足していて、古典のテキストさえ、先輩から借りて筆写 して使うほどであったが、どういうものか、あの頃入手した新刊歌集は『しろたへ』だけでなく、北原白秋の『牡丹の木(ぼく)』もあった。或いは紙の供給の割当てが、短歌には緩やかだったのだろうか。用紙の統制に関与した斎藤瀏将軍(斎藤史さんのご尊父)の力があったのでは、という人もいるが、これは憶測の域を出ない。
ともあれ私は青磁社発行の『しろたへ』の自然詠にしびれ、次いで入手した『歩道』の都市詠にしびれ、佐藤佐太郎の門下となることを決心した。終戦前後のゴタゴタの中で、佐藤先生も岩波書店をやめて郷里に帰られていたが、終戦後しばらく、札幌青磁社に籍を置き、札幌に滞在しておられたようだ。やがて上京して、焼跡のまだ生々しい羽田近くの糀谷(こうじや)に住まわれた頃、私は初めて佐太郎先生と面 会できた。それより前、阿佐ヶ谷の川村シゲンというお宅から添削の手紙を頂いたことがある。これは年譜にも全く載っていないのだが、仮住まいでもされていたのだろうか。
ともかくもそのなつかしい「青磁社」の名が、今こうして佳い形で継がれていることに、私は何かほのぼのとした思いを持つのである。
あの堂前青年も今は中年となり、辰砂や鉄釉の重厚な作品も手がける立派な陶芸家となった。どんぐりちゃんどころではないのである。が、私にはやはり初期の青磁の純朴さが忘れられない。花瓶、茶器、コーヒー碗といつか数がふえ、宮家の姫君ならぬ 私も、日常的に青磁の器を楽しんでいる昨今である。
愛とやさしさ
安藤ミツル歌集『雲と遊ぶ』

亡き父の住み給ふらむ秋空の高きに生まるる雲と遊ばむ
歌集名となった一首であろう。まるで幼い頃に還ったような屈託のないやさしさがある。安田純生氏の跋文にあるように、家族詠が多い歌集と同感するが、なかでも父母への情愛の細やかさは類を見ないほどで著者はずい分と幸せな環境のなかで、成人されたに違いない。
結婚したおおよその女性は、両親と暮したよりもはるかに永い夫との生活に根を下ろし、いつしかそこが安住の場となる。両親への愛情とは一味違う絆が育ち関わり方の比重の変化も出てくるが、この著者の場合は少々違うようだ。愛情の深さ、容量 には、人それぞれに差異があり、安藤さんは稀にみるやさしさと豊かな愛を湛えた素敵な女性と思われる。また積極的で明るいプラス指向の持主であろう。
牡蠣の殻みなさまざまな象して厳冬の日の渚に光る
寄せ植ゑの松竹梅のそれぞれを春の日ざしの大地へ移す
蓼の花持てる人くる吊橋の下ゆく水の流れのひかる
走り根に銀杏相寄りまろびゐて五月の空へ青芽を出す
ゆづりあふ峡の道なり毬(いが)の落ちはじけし栗の光りかがやく
抄出したいずれの作品にも光があり希望がある。愛を潜めた細やかな目が働いており、これらは本集のトーンとなっていて快い読後感をひき出しているようだ。
失意の眼そらせば蟻の列ありてよろこびのごと長くつづけり
磨かれし玻璃戸に春の光さし父の余命をつなぐ点滴
失意もたちまち喜びに転じ、病床にある命もいつしか活きづいてくるような把握である。この明るさの原点は、やはり生まれ育った環境とその父母にあると思われる。
少女期に母編みくれしハーフコート古き笥の底より出でぬ
すみれ草咲き誇りゐるふるさとに老い母の居て少女に戻る
半生を過ぎても色褪せることのない少女期を持つ作者。
玄関に息子のぬぎし靴持てば足の温もりわが手に伝ふ
診察に急ぎて脱ぎし夫のシャツのぬくもりふはり我が腕の中
黙したる父のごとくに立つ樫の乾ける幹に触れてあたたか
墓参への径にて母と手をつなぎ温みつたはり宝のごとし
息子、夫、父はもの(、、)を介在させたぬくもりであるが、母の場合は、直接的なぬ くもりである。宝のごとしと言い切れるほどに強い結びつきを感じると同時に、まことに素直で初初しい。
親子関係、家族の絆の稀薄が取り沙汰される昨今であるが、著者の愛情深い生き方の詰まった本集は、誠に貴重というべきであろう。
やさしき眼差し
今西秀樹歌集『実生』

「塔」に所属する著者の第一歌集。六年余の作品五一一首を収録する。カバーは空を見上げる亀のイラストであり、集中には亀を詠った佳品が多い。
日本の夏のひかりに甲羅干し亀はねつとり干涸らびてゆく
誠実かつ真摯に物事に向き合い、表現で奇を衒うことはない。生活を基盤に日々の思いを率直に詠む。会社員として多忙を極めた時期だったというが、素材の多くは仕事よりもむしろ家族、周囲の自然である。素材を直截に切り取っていく。特に子とのふれあいを描いた作品は魅力的である。
梅雨の夜を数学教へるわれと子も平方根の外へは出られぬ
この式が「わからん」といふから教へればこぼれ落ちたるおほつぶ涙
霜枯れる木の葉を分けて背後から春は来るらし伊賀越(いがごえ)の里
決して平坦な日々であったわけではなく、身体の不調もあった。しかし家族に助けられ、互いに支え合う。家族の成長の記録の側面 を併せ持つ一冊である。未知の作者でありながら、日々の躍動感がわたしにも伝わってくる。
手術なき永いひと日の日の暮れに家族四人のそろふうれしさ
わが家族の荷物をすべて運び出す傾く家の欠伸が聴こゆ
雪積もりバイトに行けぬ子は雪を投げくる幼き日のままにして
何事においても生真面目であるように見受けられる。しかし真面 目なだけではない。〈「キャプテンはゐますか」といふ電話受け子の帰るまでうれしき親ばか〉のようなそこはかとないユーモアも集中に散りばめられている。
序文で河野裕子氏は「人生を素直に肯定することの大切さを教えられた。」と記すが、わたしも大いに頷く。自然体で詠まれた作品の良さを充分に感じるのである。
忙殺の勤めから帰りやはらかく水底眠る亀を見守る
生まれくるわが子を持てるよろこびにどこか似てゐる家の建つらむ
人生に肯定的であり、前向きな姿勢が爽快さを生む。もちろん何事も順調にいくわけではない。ただ苦労が多ければ多いほど、そのあとの喜びが大きいことを知っているようである。
私も荷物をひとつに出来たらなたんぽぽのやうに飛べる気がする
子育てに一区切りついたという著者が、今後どのような短歌を紡いでゆくか楽しみである。
最後にまったくの私事になるが、わが一人娘の名は実生という。何やら身近に感じた理由のひとつである。
千五百年生きこし花ははなを生む淡墨さくらの実生を買はむ
森とひかりの物語
青木道枝歌集『森のひかり』

青木さんとは八年ほど前に「短歌21世紀」の結社で一緒だった。言葉の用い方がしっかりしていて雰囲気のある歌だったので毎月真っ先に読んでいた。いつの間にか退会されたため作品を読む機会を失っていたのだが、今回第二歌集としてまとめられた作品に再会できた。久しぶりに読んだ青木さんの歌は、森の暗さとそこに差す光の鋭さを併せ持った静かな世界であった。
黒々と土を返して薔薇の苗植ゑをり凍土となりてゆくとき
落葉掃きて林のなかに人のをりわが過ぐるとき頭を上げず
森の奥来たればここに差すひかり古き幹照らしあたたかさうないろ
森を出でぬかるむ道の照りかへし黙してバスを待ちゐる人ら
森の道たどり小さき店に人はラードを買ひてまたかへりゆく
物理学者の夫とともに海外で暮らす生活らしく、異国の風土が多く詠まれている。特に、家があったと想像される森の中での歌は魅力的だ。眼前の事象から核となるものをすくい上げて定型におさめる手法を自分のものにしている。そうしてうたわれた歌は、重苦しいまでの存在感を示し風景の広がりを見せる。「黒々と土を返して」のリアルさや、「わが過ぐるとき頭を上げず」に表れた陰影、森の奥に見つけた光を「ここに差す」と言う切実感。総じて主観にかかわる語が少なく、その分余情が深い。バスを待っている歌やラードを買って帰って行く歌になると、異国の絵画や物語を見るようである。「ぬ かるむ道の照りかへし」が上句にあってこそ人々の沈黙は重厚になり、「ラード」の具体が一首の輪郭を引き締める。青木さんはそういうところをきちんと押さえていて、長い間「アララギ」や後継誌で研鑽を積んできたことが自然と思われる。
塀のうちに支へ合ひつつ生きてゐる母と鯉らとしづかに音立て
やはらぎて表情もちて数式あり灯のした夫の構想ノート
ガス扱ふ実験室に小鳥飼はれ学生たちの付けし名をもつ
けふは三人の留学生とむかひ読むひとりが立ちてあかりを点す
故郷に一人暮らしをしている母親と、共に暮らしている夫。二人の家族に対して、作者はひとかたならぬ 思いを抱いていると想像される。しかしそれを声高に言うことはしない。「鯉らとしづかに音立て」と言い、数式の構想ノートに託すのである。こういうスタンスを貫いて、青木さんの歌は静かでかつ豊かな叙情をもって読み手の内側に響いてくる。最後に挙げた留学生たちとの歌。灯りを灯す動きを描写 しただけなのに情景が鮮やかにたちあがる。表現の妙である。
『美濃』小感
高橋亜子歌集『美濃』

岐阜で長く生活し、本集の大半の作品の場が岐阜なので『美濃』と題したと「あとがき」にある。
同じ新アララギの女流大下宣子氏が、先ごろ『志斐がたり』という歌集を纏めて、多くの話題を集め、注目を浴びた。
両歌人に共通するのは、共に作歌ばかりでなく、多方面に知的な関心を持ち、積極的な行動を伴って、それらを作品化しているというところである。
岐阜県生まれの、あるいは岐阜県にゆかりのある女性には、かかる生き方が自ずと身につくのかと思われるくらいである。と言うのは、私の母も古い時代の岐阜県生まれで、岐阜県下初めて東京女高師(現お茶の水大)に入り、「青鞜」の文学運動に加わって、諸種の活動をした女性であったからである。そういう親近感も加わって、この歌集も読み、その感想を綴ってみたくなった次第である。
新しきコートの色をほめくれし友と別れてブローチを買ふ
風邪癒えし夫は再び我を退け厚きデーターを食卓に読む
切り詰めしのうぜんかづら再びの濃き花咲きて夏ゆかむとす
夕刊なきことにも馴れて夕方は溜池に鳴く牛蛙聞く
灯を寄せてミシン踏む母のかたはらに夜々を眠りき我は幼く
このステップ踊れるもあと何年かリズム激しく踏みつつ思ふ
北の山覆ひし靄の暖かく夕あかりして太き虹立つ
年代順に二十五年間分が収録されている中から、巻頭より各年度一首ずつを引いてみた。こうして見ると、素材的にも、感覚的にも、様々な分野に関心を有し、感銘を獲得しようとしていることが読み取れる。
この国にとりても悲しみなるを知るアルバカーキ原子力博物館に
抽象画以前のピカソのリトグラフ丹念な細かき線の目立ちぬ
ハングルを学びて知りぬその母音河内方言に残りてあるを
この天体に我ひとり居る心地して伊吹山頂にあかときを待つ
知多の岬今日飛び発つかひたすらに石蕗(つは)に縋れるこの渡り蝶
続けて引いていってもこの感じが少しも損なわれることはない。本集の特色は、まさにこの弛(たゆ)みない関心の継読と、それを感受する精神の進取性と、その表現化への努力の実践と言うことができるだろう。
生活と心の「秋草」
河野君江歌集『秋草抄』

これの世に争い生きし父母の墓は小さし秋草のなか
古里の段だん畑は土手となり境もあらず深き秋草
離郷して六十余年屋敷あとにぺんぺん草とかぼちゃの黄花
寒村となりてしまいぬ古里の父母の墓に紅葉散りいる
すり足に畳を歩きつつ思い出づ晩年にかく歩きいし母の足音
他人の手のごと皺ばみしをかざしおり後何年働けるだろう
三首目のように河野さんは離郷して半世紀を〈知人なきこの地に長く住み慣れてびわ湖を窓に見つつ過ぎゆく〉と「他国」に腰を据え生きている。いわば多くの女性たちが代々に渡って累ねてきた生の位 相なのだ。「後何年働けるだろう」には、勤勉に働いて生きる日本人女性の典型がある。そんな河野さんが日常に視点を据えたんたんと歌ったのがこの歌集。日常といってもなかなか起伏に富んでいて、歌いかたによってはいくらでも人生ドラマになるのだが、その感情は細部に語らせ、細部からドラマを立ち上がらせる。引用二、三首目の下二句でそれらは分かる。この秋草のおどろは作者の内心をよく語っていよう。
昨日まで畑の指図をしていしに硬くなりゆく指組まれている
四十年夫が育てし三百坪トマトも茄子もひかりつつ太る
泣き夫が植えし山芋の根は深く掘りあぐねいる幾度も休み
一巻のピークは夫を哀悼する一連。しかし「跋」で池本一郎氏も指摘しているが直接悲しみを言う言葉はない。二首目の下二句は夫が育てそれを守ってゆこうとする作者の心を語っている。「ひかりつつ太る」が実にいい。三首目の「山芋の根」は作者の心に根を深く下ろしている夫の存在。亡きのちも夫がいかに深く作者に生きているか。悲しみはそのような形で「根は深く」降ろす。そこに無限の悲しみがある。
家中で一番ノッポの無口の有衣子時々吾を後ろより抱く
花びらを踏みて気づけり梅雨空の高きにありて朴の花白し
裏木戸に棕櫚の木ありしは何時のこと遠き日のその棕櫚の風音
二首目など作者の観察眼の確かさを語っている。三首目に注目した。なんという「棕櫚の風音」だろうか。遠い日の「裏木戸」の棕櫚の風音。悲しいとも寂しいとも言わないが、生きていることの絶対の悲しさを含んだ思い。それは〈物を忘れ添いくる心のさみしさは私がだんだん遠くなること〉と歌う生きていることの「遠くなる」のシビアな認識の切なさにつながる。こんな風に物に、観察眼に心を預ける歌い方が手の内なのだ。
引用一首目。「永田和宏」「裕子」の実名が登場する家族詠も微笑ましく、ワンショットはなかなか楽しい。この歌「ノッポの無口」が生きている。こんな心の通 う家族たちを「後より抱」かれると据える心の暖かさ。歌集題とした「秋草」とは、河野さんの愛しく生きている生活と心の象徴なのだ。
確かな温もり
須藤冨美子歌集『秋の麒麟』
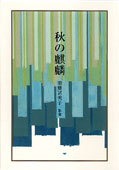
『秋の麒麟』には家族との生活を愛する作者の日常が生き生きと綴られ、生活と作歌が密接であることが窺われる。
みどり児のオブラートのような爪を切る老眼鏡に眼を凝らしつつ
臆病な少年に見する逆上がりやっとこなしぬ ああ老いにけり
作者は研究の責務を負う娘のため孫の育児を引き受け、気力、体力を要する日々を過ごしている。「オブラートのような爪」には切りにくい赤児の爪の柔らかさ薄さが見事に喩えられている。また自ら逆上がりをして孫に教える作者、「やっとこなしぬ 」からは息切れまでも伝わってくる。そんな家族へのひたむきな愛情は、実は母から授かったようだ。あとがきに、作者が十六歳の時に母が発病、末子の作者の成人まではと手術を受けたが成人式を前に亡くなったとある。遺品に短歌ノートがあったことが、作者が短歌を作るきっかけとなった。
成人式見ずに逝きたる母の歌にわれの二十歳を詠みし二首あり
きゅっきゅっと音のするまで拭くのです廊下を拭くたび母の声する
母の几帳面な気質、娘に今しつけねばとの切実な思いが滲んでいる。この母の情愛は作者の姿に投影されて、一集の中に見え隠れしていると感じた。
童話も書いているという作者。一首一首に描かれる家族の姿は物語の主人公のように輝きを放っていることも特徴だ。
クレヨンのブルーの線ののびやかにあきらは襖に力作を描く
夕光が窓を染めおり白壁に泣き虫小僧が張り付いている
難解な言葉や派手な比喩を押さえた素朴な言葉の連なりが、等身大の日常を確かな温もりを伴って伝えている。
今なればわれも籠りの子となるか老いづきてなお群れを恐れる
幼い時に戦争を体験した故に抱えてしまった集団への恐れなのか、普段は気づかない深層の表れなのか。一集の中で、作者が自身へと視線を向けた作品が私には印象深い。
左手だけ置かれていたらわがものと判るだろうか鏡に映す
自分はどこ迄自分を知っているのかという問いかけは普遍的で、鏡にわざわざ左手を映してみる行為は象徴的だ。
笑うことが罪であるように口きつく結びし写真ばかりのアルバム
来校者バッヂ付け行く授業参観 安全な場所ではない小学校
時代を詠んだこれらの歌が一集に陰影をもたらしている。
じわじわが好き
高野公彦
伊藤一彦
津金規雄歌集『シリーズ牧水賞の歌人たちvol.1 高野公彦』

シリーズ第一巻。新旧の評論・エッセイ・インタビュー・住時の写 真など、貴重な資料が豊富である。既発表部分は作品に直結する内容が多く、新たに収録された部分は人間そのものの理解を深める内容が多いようだ。
中でも、監修の伊藤一彦によるインタビューは三十八ページにも及ぶ。近くで接していると、故郷の思い出や生い立ちなどを含め、人間は徐々にわかった気になる。しかし、改まって質問しない限り、個々の話と作品がどのような接点を持つのかを聞き漏らしてしまう。伊藤氏はその点を積極的に質問し、高野も饒舌に答えているようだ。
例えば、小さいときから言葉や文字に関心があったかとの問いに、高校時代に読んだ吉川英治『宮本武蔵』の中の「いばり」という語に触れて、
「いばり」とは小便のことなんだけど、その「いばり」という言葉に出会って、おもしろい言葉があるなと思った。言葉というものを意識したのは、そのときがはじめてです。
と答える。今につながる〈言葉から発想〉の原初として興味深い。また、のち『甘雨』に収録される、愛媛方言(ぶげんしゃ、いもがい、あんき、など)を使用した約五十首の作品について、
言葉を短歌のかたちで残したいということで、言葉に残したいから歌をつくっているんです。
と述べる件がある。高野短歌の中心をなす考えであろう。(編集の津金規雄による歌集タイトルについてのインタビューもある。そこでも、汽水、淡青、天泣、渾円球など、言葉を発想の契機にして、作品から歌集タイトルへ進んだ経緯を述べている。)
またあるところでは、
僕は、いつもじわじわなんですよね。わりにゆっくりというか、ぱあっと目立つというタイプではない。作品もそうですし、自分の生き方としても、ゆっくりじわじわが好きなんです。
と言う。この自己認識のセリフを本人の口から引き出せたことは、この企画の大きな得点である。
〈自歌自注〉では「白き霧ながるる夜の草の園に自転車はほそきつばさ濡れたり」について、「〈見た風景〉でなく、〈見たい風景〉を詠んだといへるかもしれない。」と言い、作歌時にはハンドルをつばさに見立てたわけではなく、「あくまでも直感で詠んだ歌である。」と述べている。この点、高野作品を理解する上での貴重な自解であった。
高野研究の第一歩として、作品・人間を重ね合わせて理解できる一冊。企画の勝利と言えよう。
ふかい哀歓
河西かつ子歌集『白墨家族』

筆太に楷書で書きし履歴書のはじめに 平民三樹尾次女藤巻かつ子
老眼鏡に重ねて見たる天眼鏡おおしっかり見えた欝の字
供出の玄米俵六十キロ背負いて運びし十六歳の秋
歌集の巻頭に近い章より引いた三首からは、くっきりと作者像が浮かび上って来る。明治維新の翌年設けられた平民という身分呼称が個人名の上に置かれた時代は敗戦の二年後まで続く。作者がふと手にした履歴書は一つの時代のありようを確かに読者に伝え得ている。二首目。欝状態にある心を詠もうとしても欝の字は老眼の作者の手にはおえない。天眼鏡を併用することで字画を捉えた瞬間「欝」の字は意味を離れて輝くようだ。三首目の「玄米俵六十キロ」の表現は一首目の「筆太に楷書」の筆跡と重なる。戦時下の青春期に全力で何事にも取り組む女学生であったことが作者の現在の作歌姿勢につながっている。
日常の折々の心象を具体的なモノや場面に託して詠む態度に歳月の年輪が重なり巧まぬ ユーモアが漂って来る。
これ母さんこれはお兄ちゃん秋日さす道に描きたる白墨家族
中東の戦況解説する息子微に入り遂に我を眠らす
息子の背(せな)にすがりオートバイの走るなり吾はピンクのシャツを羽織って
家族詠は常凡になりがちだが、甘さをひかえ一定の距離を置いた作品が成功している。自動車の入り込まない路地に差し込む秋の陽光に、作者の家族の顔が浮かび上がる。白墨という頼りない線で幼子が描く家族像に、愛別 離苦を知る年齢にある作者は思いがけない位つよい印象を受けたのだろう。家族である時間の限りを知るゆえにかけがえのないものとして「白墨家族」という歌集名を選ばれたのだろう。続く二首は作者の現在の幸福を物語る歌であるが、作品の場面 を客観的に眺める眼差しがあり、ほのぼのとしたなかの余韻が愉しい。
ガリラヤ湖岬にオカリナ吹く人のありて讃美歌湖面渡り来
貧しさの最中に死にし嬰児に購えなかったりんごを二つ
コクコクと喉を鳴らして乳を飲む赤子の額汗にじみたり
一首目は「聖地巡礼」の旅の途上の作。作者は表立てないがキリスト教者である宗教観がほのかな慰籍となってこの集に底流している。哀歓のふかさを味わった作者であるからこそ、嬰児の生の懸命をうたいとどめ得たのである。

